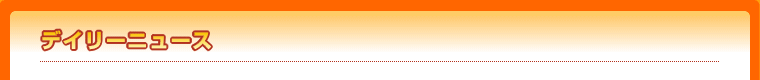2005年11月24日
「完全な一日」 Q&A
上映終了後、ジョアナ・ハジトゥーマ監督とカリル・ジョレイジュ監督をお迎えしてQ&Aが行われました。
林ディレクター: この作品は、スイスのロカルノ映画祭で国際批評家連盟賞とドンキホーテ賞の両方を獲られたレバノン映画です。今朝到着されたばかりでお疲れと思いますが、一言ずつご挨拶お願いします。
ジョレイジュ監督:まずは東京に来られてとても嬉しいです。関係者の皆さん、映画祭に呼んでいただき本当に感謝しています。この映画は私の個人的な思い出から出発しているものです。というのも、私の叔父が17,000人の内戦以降行方不明になっている人の1人だったのです。この行方不明者を扱うことの興味深さというのは、現代の問題を扱うことにもなるということです。つまり、今、レバノンでは内戦からの復興が目覚しく進んでいますが、一方で彼らは未だ帰ってきていないのです。ですから、この映画に取り組むにあたっての私たちの問題は現代と歴史ということにどう取り組むかということ、言い換えれば、直線的な物語を語ることができない歴史をどう映画として取り込むかということでした。ですから、私たちはもちろん物語あるいは歴史という過去を持っていますけれども、その過去からの贈り物を敢えて覆すことで、むしろ未来に向かおうと、ある種モダニスト的なアプローチでこの作品に臨みました。そうすることである種の緊張感、ヒステリックなまでの緊張感を作品に持たせようとしました。
ハジトゥーマ監督: 私たちの住んでいるレバノンという社会は大変に共同体的な側面が強い社会です。その中ではなかなか個人として行動することが難しい社会だとも言えます。その問題というのは実はレバノンということ以上に大きな問題だと考えています。私たちが注目した1つの大きな問題はリズムの問題です。例えば、映画の中で(主人公の)母親はその社会の構造の中で、夫が実は死んでいるという立場で行動することは許されていない、夫が行方不明になってもう何年も経っているのに、あたかも夫がいるかのように生活しなければならず、一方で息子の方はガールフレンドを自分の頭の中から追い去ることができない、忘れ去ることができないのです。つまり、現代社会というのは極めて速いリズムで動いています。しかし本当にその速いリズムというのは私たちにとってそんなに大事なことなのかということを問いかけようと思ったのです。ゆっくりしたリズムではなぜいけないのかという問題があると思います。もう一つ私たちが注目したのはリズムと関わることですが、人間の身体という問題です。つまり、人間の身体をどうみるのか。その点で特に興味深かったのは、マレクという息子の人物ですけれど、最初、寝ているところから始まって、しばしば寝ているシーンもありますけれど、一方で基本的には極めて活動的な、いつも体が動いているような人物です。彼のような身体を、特にベイルートのような町、極めて活動的で躍動感のある都市の中においたらどのように見えるのかということに非常に興味を持ちながら演出しました。最後に、この映画の演出についてもう1つ言いたいことがあります。この映画は極めて低予算でして、現実を再現するという通常、劇映画でやる方法は取ることができませんでしたし、敢えて取ろうともしませんでした。例えば、エキストラというものは一切使っていません。交通渋滞のシーンがあれば本当の交通渋滞の中で撮影しましたし、海岸のシーンを撮る時にも、普通の映画撮影のように通行人を止めて、他人が入って来れない状態を作って撮影するのではなく、本当にその場で海岸に遊びに来ている人たちがそのまま写ってしまうような撮り方を敢えてしてみました。そのように、登場人物を現実の中に挿入していくというやり方でやってみたのです。敢えてこのやり方についてドキュメンタリーという言葉を使おうとは思いませんが、リアリティの中に登場人物を挿入していくというその一方で、むしろ一つ一つ、極めて美的に作りこまれた構図を作ろうとしました。この2つの、ある種ドキュメンタリー的スタイルとその一方で作りこまれた構図という2つのスタイルが映画の中で衝突することでどのようなことが現れてくるのかということにも興味を持ちながら作りました。
ジョレイジュ監督: もう1つ演出の上でやったことというのは、例えば登場人物をきちっとしたフレームの中におさめて、じっと待ちながらその人物の身体に何が起こるのかということを見ようとしたのです。この映画には実は脚本というものはありませんし、出演者は母親役の人以外はすべてプロの俳優ではありません。その人たちを現実や物語の状況の中に置くことで何が起こるのかということを見つめていこうと思って作った作品です。
Q:煙草がこの映画の中で重要な役割を占めていると思うんですが、これは偶然なんでしょうか、それとも何か意味があるのでしょうか。
ジョレイジュ監督: 一つにはレバノンでは喫煙は大変に盛んで、レバノン人の多くが大量に煙草を吸います。煙草の問題で1つ興味があるのはその中毒性、依存性がある問題だということですね。もう1つ興味があったのは、煙草というのは吸えばどういう効果があるのかが分かっているのに、皆、煙草を止めずに吸い続ける、何本も吸ってしまう、それはなぜなのかということです。これは極めて映画的な問題だと思っています。それで、敢えて煙草というものを使ってみました。
ハジトゥーマ監督: もう一つ、中毒という問題に付け加えて言うと、例えば、主人公の青年はガールフレンドにある種中毒というか、依存症的にとりつかれている状態にあります。これはもっと大きな意味で言えば社会の問題として、レバノンは15年から17年の長い内線を経験した国ですから、そういう意味では私たちは戦争の中毒になっている、戦争依存症になってしまっているとも言えると思います。例えば、夜のシーンをこの映画で見せていますが、皆、夜通し外に出て遊んでいるんですが、なぜ夜に落ちついて寝ていられなくて、外に出て行くのかということは、レバノン人が長い内戦の歴史によってある種の戦争中毒状態になっていることと何か関係があるのではないかと思えるわけです。つまり、落ち着いてゆっくりしていることができない、常に緊張状態になければいけないという感覚がレバノン人にあるのではないかと思うのです。
Q:日本人の目から見て、少しよく分からなかったのは母親と息子の関係が身体的にも精神的にも非常に密接な感じがしたんですけれども、2人が非常に孤独な家族として社会の中で苦しんでいるからなのか、レバノン人の普通のコミュニケーションとして示されているのでしょうか。
ジョレイジュ監督:私は社会学者ではないので上手く答えられるかどうか分かりませんが、できるだけきちんと答えてみようと思います。一つには、この家庭という特別な状況の中で母親が息子にいろんなものを投影しているのだろうと思います。というのは、当然夫がいなくなって何年も経っているので、そこにいろんな役割を求めてしまう、投影してしまう ― そこには行方不明になった父の役割、家長の役割をも息子に求めてしまうという部分があるわけです。もう一つ重要なのは、レバノンの文化の特異性かもしれませんが、レバノン社会においては身体との関係というのは極めて重要なのです。つまり、人に会ってもすぐに抱き合ったり、肩をたたいたり、キスをしたりという身体的接触は日常的に行われています。そのようにレバノンの文化というのは大変に肉体的であり、身体的であり、官能的な文化です。そこで、特にこの母親の役割で重要なのは、十何年間も夫が行方不明であるということは彼女にとっては触るべき身体というものがない、そこで彼女にとっていわゆる肉体の不在、自分自身にとって気持ちの中で肉体というものがないということが彼女にとって大変大きな問題になっているだろうと思います。
ハジトゥーマ監督:もう一つ付け加えたいのは、先ほども言ったかとは思いますが、レバノン社会は共同体的な側面の強い社会です。従って、その中での家族というのは極めて大きな役割を持っています。レバノン人にとっては、家族は非常に大切であり、ひとりひとりの人間は家族に依存していますし、家族もまた私たちひとりひとりに依存しています。私たちは毎日のように電話を掛け合ったり、いろいろ話をしたりしています。で、そういった家族の絆が異常に強い社会の中で、しばしば人間は個人として自由となることは難しくなるのです。そういった社会の強い家族の絆の中で、家族と縁を切ることなく、しかし一方で1人の人間として自由に生きるということがどういうふうにすればできるのかが大きな問題であり、私たちが作る全ての作品がそういう意味では、私たちの告白の部分、その自分たちが一番悩んでいる問題について語っていることになると私たちには思えます。
投稿者 FILMeX : 2005年11月24日 19:00