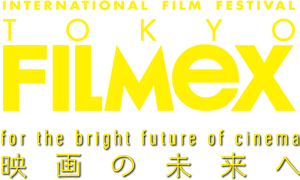11月27日、オープンしたばかりの台湾文化センターにて、ツァイ・ミンリャン監督の短編最新作『秋日』が上映され、上映後には、ツァイ監督、俳優のリー・カンションさん、野上照代さんをゲストに迎えてトークショーが行われた。『秋日』は、黒澤明監督作品のスクリプターを長く務めた野上照代さんをとらえた作品で、昨年11月の東京フィルメックスでツァイ監督とリーさんが来日した際に撮影された。上映前には、台湾文化センターの所長、 朱文清さんからゲストと観客に向けて歓迎の言葉が述べられた。
11月27日、オープンしたばかりの台湾文化センターにて、ツァイ・ミンリャン監督の短編最新作『秋日』が上映され、上映後には、ツァイ監督、俳優のリー・カンションさん、野上照代さんをゲストに迎えてトークショーが行われた。『秋日』は、黒澤明監督作品のスクリプターを長く務めた野上照代さんをとらえた作品で、昨年11月の東京フィルメックスでツァイ監督とリーさんが来日した際に撮影された。上映前には、台湾文化センターの所長、 朱文清さんからゲストと観客に向けて歓迎の言葉が述べられた。
上映後、さっそく司会の市山尚三東京フィルメックス・プログラムディレクターから、作品について感想を問われ、ツァイ監督は「シンプルな構成ですが、僕にとってとても大事な作品です。映像というよりも、野上さんを描いた一幅の絵画だと思っています。野上さんとは20年ほど親交がありますが、数年前に突然彼女を撮りたくなりました。この作品は、日本の皆さんへのプレゼントです」と述べた。本作を初めてご覧になったという野上さんは、「もうびっくりしました。原節子さんみたいな女優ならともかく、私のような年寄りの顔を見せられて、みなさん、ご迷惑をおかけしました」と応じて、会場から笑いを誘った。
 また、独特の長回しについて野上さんから指摘されると、「いつも野上さんから長さについて批判されるのですが、今回、せっかくなので、長回しで撮られる役者の気持ちを味わってもらいました。上手に対応なさっていましたよ」とツァイ監督。野上さんは、「シャオカン(小康:リーさんの愛称)もずいぶん我慢しているわね」と言うと、リーさんが「ツァイ監督の作品への出演は、いつも試練です。デジタルになって余計に長くなりました」と野上さんに同調する一幕も。
また、独特の長回しについて野上さんから指摘されると、「いつも野上さんから長さについて批判されるのですが、今回、せっかくなので、長回しで撮られる役者の気持ちを味わってもらいました。上手に対応なさっていましたよ」とツァイ監督。野上さんは、「シャオカン(小康:リーさんの愛称)もずいぶん我慢しているわね」と言うと、リーさんが「ツァイ監督の作品への出演は、いつも試練です。デジタルになって余計に長くなりました」と野上さんに同調する一幕も。
続いて、本作の撮影場所について話が及んだ。冒頭、野上さんの音声のみの場面は、井伏鱒二の額がかかっている野上さんお気に入りの喫茶店で撮影されたとか。野上さんが字幕翻訳家の寺尾次郎さんを相手に話している内容について、ツァイ監督は何もわからないまま撮影、編集を行い、字幕をつける段になってようやく知ったという。撮影時は雰囲気も撮れた画も良かったそうだが、最終的に画を消してしまったのは、画があるとドキュメンタリーになってしまうからで、この作品は「聴くことと観ることに特化した作品」だと説明。監督自身が干渉しない形で、映画の概念で野上さんを撮りたかったのだという。「謝謝と言うべきでしょうか」と野上さん。
 終盤の東宝撮影所での撮影では、自分が映る意味はないだろうとリーさんから抗議を受けたというツァイ監督。「でも、僕はシャオカンに野上さんの横にいて欲しかった。それが必要でした。シャオカンがいて、野上さんがいて、それを撮っている僕がいる。関係づけや理由づけは必要でなく、そこにいるという映画の時空を感じていました」と振り返った。加えて、「野上さんを撮るのは、ジャングルの中にいるライオンを撮るような感じ。撮らせていただければそれで満足ですから」とユーモアたっぷりに評したツァイ監督に対して、「シャオカンと一緒に撮影できたから喜びましょう」と応じた野上さん。リーさんも穏やかな微笑みを浮かべて頷いた。
終盤の東宝撮影所での撮影では、自分が映る意味はないだろうとリーさんから抗議を受けたというツァイ監督。「でも、僕はシャオカンに野上さんの横にいて欲しかった。それが必要でした。シャオカンがいて、野上さんがいて、それを撮っている僕がいる。関係づけや理由づけは必要でなく、そこにいるという映画の時空を感じていました」と振り返った。加えて、「野上さんを撮るのは、ジャングルの中にいるライオンを撮るような感じ。撮らせていただければそれで満足ですから」とユーモアたっぷりに評したツァイ監督に対して、「シャオカンと一緒に撮影できたから喜びましょう」と応じた野上さん。リーさんも穏やかな微笑みを浮かべて頷いた。
そして、「ツァイ監督の良さは、一切説明をしないところ、観客に媚びないところ、度胸のあるところ」と野上さんが何度も強調すると、ツァイ監督は次のように語った。
 「これから作品を撮る上で、シャオカンが健康でいてくれることを願っています。観客のため、映画のためにではなく、自分のために映画を作っているわけで、そのためにも彼が存在してくれないと撮れません。自分の作品は、自分の命運や人生と密接に関わるものを撮りたくて、自分の命運や人生を懸けて創作していきたいのです。長い、長いと言われますが、それは僕の世界や社会に対する見方で、ストーリーを提供するよりも、そこにある存在を見つめるという感覚なのです。僕が願う映画制作の環境としては、観客のためだけではない道も残して欲しいということです」
「これから作品を撮る上で、シャオカンが健康でいてくれることを願っています。観客のため、映画のためにではなく、自分のために映画を作っているわけで、そのためにも彼が存在してくれないと撮れません。自分の作品は、自分の命運や人生と密接に関わるものを撮りたくて、自分の命運や人生を懸けて創作していきたいのです。長い、長いと言われますが、それは僕の世界や社会に対する見方で、ストーリーを提供するよりも、そこにある存在を見つめるという感覚なのです。僕が願う映画制作の環境としては、観客のためだけではない道も残して欲しいということです」
それに対して野上さんは、「興行を無視することのできない映画業界にあって、観客に媚びずに自分の個性を持ち続けることは難しいこと」としながら、「そういう意味でご自分を鍛えているのだと思います。世界にひとりぐらいそういう監督がいてもいいのではないかしら。良い結論じゃない?」と茶目っ気たっぷりにフォロー。
すると、すかさずツァイ監督が「僕は辛いとは思っていません。むしろ、羨ましがられています」と応じた。ツァイ監督によると、作品が劇場公開されずとも、美術館の展示品として上映される機会があり、新たな販路を確保しているのだとか。そして、今回『秋日』の上映にあたり、椅子ではなく床に座って観るよう指示された観客に、「今日、みなさんに床に座って観ていただいた理由は、映画を観るのは劇場だけではないということを知っていただきたかったから」と説明した。
さらに観客からは、どのようにして長回しというスタイルに辿り着いたのかという質問が寄せられた。ツァイ監督にとっての興味は、映画の持つ時間性とリアルなものを近づけることで、アングルをあれこれと変えて撮るよりも、ひとつのアングルでずっと見る方が自身にとってリアルだと感じられるのだとか。例えば、ひとつのカットを通して、自分の持っている何らかの感覚、思っていることを表現してもらおうとするとき、出演者がそれを表現するにはどうしても時間がかかってしまう。出演者が頭の中から思考や段取りを消して、自然な環境に溶け込んだ時が一番いい演技の状態だと思えるのだそうだ。野上さんによると黒沢監督も似たような撮影スタイルの側面をお持ちだったようで、きちんとした被写体が作り上げられていないとカメラを回さなかったとのエピソードを明かしてくれた。
日本映画に学んだところも多く、特に日本映画の黄金期とも言える、小津安二郎監督、成瀬巳喜男監督、黒沢明監督の作品を好んで観たというツァイ監督。本作を日本映画にも捧げたいと語り、終始ユーモアにあふれた和やかな雰囲気のトークショーが終了。熱心な観客たちも、3人の魅力をたっぷり堪能した様子だった。
第16回東京フィルメックスでは、11月28日(土)から12月4日(金)まで有楽町スバル座にて<特集上映 ツァイ・ミンリャン>(共催:台湾文化部、台北駐日経済文化代表処台湾文化センター)を開催している。ぜひこの機会に足を運んで、ツァイ監督の作品に触れていただきたい。
(取材・文:海野由子、撮影:白畑留美)