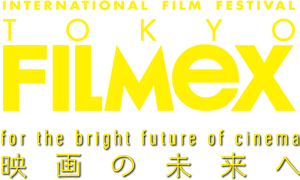11月27日、有楽町朝日ホールにてコンペティション作品『人質交換』が上映された。上映後のQ&Aにはレムトン・シエガ・ズアゾラ監督、俳優のディオン・モンサントさん、プロデューサーのビアンカ・バルブエナさん、アソシエイト・プロデューサーで撮影を担当したブラッドリー・リウさんが登壇した。監督自身が誘拐された事件を題材に、マルコス政権末期のフィリピンの不安定な社会を97分間ワンカットの驚異的な映像で描いている。
11月27日、有楽町朝日ホールにてコンペティション作品『人質交換』が上映された。上映後のQ&Aにはレムトン・シエガ・ズアゾラ監督、俳優のディオン・モンサントさん、プロデューサーのビアンカ・バルブエナさん、アソシエイト・プロデューサーで撮影を担当したブラッドリー・リウさんが登壇した。監督自身が誘拐された事件を題材に、マルコス政権末期のフィリピンの不安定な社会を97分間ワンカットの驚異的な映像で描いている。
バルブエナさんは東京フィルメックスとベルリン国際映画祭が共催する映画人材育成事業タレント・キャンパス・トーキョー(現タレンツ・トーキョー)の2012年の修了生。「再び東京を訪れることができて嬉しい」と喜びを語った。
客席との質疑応答に移ると、「ワンカットで苦労したところは?」という質問が上がった。リウさんは撮影監督ルエル・マンテプエストさんの補佐として現場にいたが、彼はカメラを回しながら照明のスイッチングを無線で指示するという「まるで舞台の振りつけをしているような進行をしていた」と振り返った。リハーサルと本番で監督の演出が変わることがあり、どうなるか予測不可能だった、と苦労を語った。
 主演のモンサントさんは撮影について「本当に苦しかった!」と振り返った。監督からは舞台の演技を要求されたが、実際には舞台ではなく映画なので、映画の演技と舞台の演技を自分の中で組み合わせる必要があったのだという。「しかもワンカットで撮っているので、泣きわめくシーンを撮った次の瞬間にはもう笑顔のシーンに入らなければならない。気持ちを切り替えるのが非常に難しく、おかしくなりそうでした」
主演のモンサントさんは撮影について「本当に苦しかった!」と振り返った。監督からは舞台の演技を要求されたが、実際には舞台ではなく映画なので、映画の演技と舞台の演技を自分の中で組み合わせる必要があったのだという。「しかもワンカットで撮っているので、泣きわめくシーンを撮った次の瞬間にはもう笑顔のシーンに入らなければならない。気持ちを切り替えるのが非常に難しく、おかしくなりそうでした」
続いての質問は、ワンカットにした理由を問うもの。「ワンカット撮影は以前の作品でも使用した手法で、自分にとってやりやすい」とズアソラ監督。今回のテーマを撮るのにふさわしい方法でもあったという。エグゼクティブ・プロデューサーのブリランテ・メンドーサ監督は当初このやり方に反対していたが、長い議論の末に説得したのだという。
誘拐された当時、ズアソラ監督は2歳で、当然ながら何も覚えていなかった。そこで当時事件に関わった人々に話を聞くことから始めたという。取材を重ねるうち、「同じ出来事にも関わらず、それぞれの人が違った形で記憶している」と気づいたそうだ。時系列はさまざまに入れ替わり、その人にとって大切でない事柄は抜け落ちたり、反対に特別な感情で彩られていることもある。「それぞれの人の記憶に残っている場面をつなぎ合わせていく、という映画を作りたいと思いました」と説明し、そのやり方を「心の中では、グルグルと記憶が巡っている。カメラを持って心の中に入り込み、そのさまをワンテイクで撮る」と表現した。
 続いて手を上げたのは、映画史家でベルリン国際映画祭フォーラム部門創設者のウルリッヒ・グレゴールさん。「この映画がどのように作り上げられたか興味を持ちました」と、セットと撮影スケジュールについて質問した。
続いて手を上げたのは、映画史家でベルリン国際映画祭フォーラム部門創設者のウルリッヒ・グレゴールさん。「この映画がどのように作り上げられたか興味を持ちました」と、セットと撮影スケジュールについて質問した。
撮影は8回やり直したという。「演技のミスや技術的なトラブルで最初から撮り直しになるたびに、セットの中から憤怒の声が聞こえてきて、私がどんどん嫌われていきました」とズアゾラ監督が述べると、ほかの登壇者は苦笑で応じた。
ロケハンでは適当な場所が見つからず、セットを作ることになったが、時間がなかったのでわずか3日で組み上げたという。これについては、プロデューサーのバルブエナさんが補足した。「セットは大きな倉庫の中に作りました。可動式の仕切りを作り、カメラを動かすスペース、さらに俳優が衣装替えをする部屋を作りました」。サウンドについては、同時録音が理想だったが技術的に難しかったので、マイクで音を拾ってダビングした。ダビング作業には苦労し、2ヶ月を要したという。リハーサルは3〜4日、撮影は1日で完了した。
8回やり直したという撮影について、「7回目のテイクがすごく良かったのに、技術トラブルでデータがダメになってしまった。みんなショックを受けたが「これは幽霊が出たからだ」と超常現象のせいにして、気持ちを落ち着かせた」という裏話も飛び出した。ようやくうまく行った8回目のテイクだが、監督一人が納得していなかった。しかし時間はすでに午前3時。疲れきっていたスタッフはみんなで「良いものが撮れたじゃないか」と監督を丸め込んだという。
グレゴールさんからさらに、「ロシアのアレクサンドル・ソクーロフや、ゼバスティアン・シッパー(『ヴィクトリア』(15))のようなワンカットの手法を使う監督を意識したのか?」と問われると、ズアゾラ監督は独自のスタイルで進化させたものだと説明した。高校時代にコミュニティ演劇に携わっていた監督は、大学時代に興味を持った映画制作にあたって演劇のやり方(一度演技が始まったらそのまま最後まで続ける)を取り入れたのだという。ズアソラ監督の長編第一作“Ang damgo ni Eleuteria”(10)はアジア映画初の全編ワンカット作品と言われているそう。「このやり方が映画の手法としては間違っているのではないかと心配していたので、他にもワンカットで撮る監督がいることを知って、安心しました」
最後に林ディレクターが、ラストシーンの”The truth is there”(真実はここにある)というセリフについて質問した。監督はこれについて「マルコス独裁の時代に、反政府、反大統領の発言をした人は次々に拉致され、二度と表舞台に出てくることはありませんでした。私の事件は政府や警察にとってサクセスストーリーになってしまった。司法や警察が機能していることの象徴のように扱われてしまったのです。しかし、その裏には何があったのか。それが“真実はここにある”という意味なのです」と語った。顔を布で覆った人々は、行方不明者“デサパラシード”の亡霊。「子どもが救出されるというハッピーエンドの裏で、大量の拉致や迫害が政府によって行われているという真実を観客の前に示すという役割を、亡霊たちが担っています」と語った。バルブエナさんが「“真実はここにある”までのシーンは人工的に作られていて、警察や軍が自分たちの救出作戦をショーとして見せる舞台という設定になっています。ところが最後のシーンは自然の光の中で、真実が示されるのです」と付け加えた。
話題は尽きず、予定時間を大幅に過ぎたQ&Aはここで終了。4名のゲストに大きな拍手が贈られた。
(取材・文:谷口秀平、撮影:明田川志保、白畑留美)