第9回東京フィルメックス
ぴあプレリザーブ 10/24(金)より開始!
申込み受付:10/24(金) 11:00~2008/10/30(木) 11:00
詳細は、チケットぴあのサイトをご覧下さい。
ニュース/事務局からのお知らせ
「テヒリーム」がシネフィル・イマジカで放映されます
2007年の第8回東京フィルメックスのコンペティションで上映され、最優秀作品賞を受賞した、ラファエル・ナジャリ監督の「テヒリーム」がシネフィル・イマジカで放映されます。
〈放映日時〉
11月16日 24:10
11月21日 19:15
11月25日 6:00
11月27日 17:00
父親の失踪で揺れ動くユダヤ教聖職者の家族のドラマ。
本映画祭では「国や宗教を超越し、独自な表現方法で語られている国際的な映画作品」と賞されました。
是非ご覧下さい。
第8回東京フィルメックス Q&A
第8回東京フィルメックス トークイベント「イスラエル映画最前線」
第8回東京フィルメックス クロージングセレモニー&授賞式
蔵原惟繕監督「ある脅迫」の試写会を開催いたします。
既にお知らせしていた通り、第9回東京フィルメックスでは「蔵原惟繕監督特集~狂熱の季節~」と題して、蔵原監督が1950-60年代の日活で意欲的に作品を発表していた中から、東京国立近代美術館フィルムセンターとの共催により、傑作12本を英語字幕付きニュープリント(一部作品を除く)で上映いたします。
今回、映画祭のプレイベントとして、ラインナップの中から「ある脅迫」の試写会を開催いたします。この試写会に、フィルメックスの公式サイトをご覧の皆様もご招待いたします。
いち早く、蔵原作品の魅力に触れるチャンス!
奮ってご応募ください。
■東京フィルメックス プレイベント「ある脅迫」特別試写会
○日時:10月7日(火) 18:00開場、18:30トークイベント開始
※上映前に、市山尚三プログラム・ディレクターとゲストによるトークイベントを予定しております。(約30分)
○会場:東京国立近代美術館フィルムセンター 小ホール(B1F)
東京都中央区京橋3-7-6
東京メトロ銀座線京橋駅、出口1から昭和通り方向へ徒歩1分
東京メトロ浅草線宝町駅、出口A4から中央通り方向へ徒歩1分
○上映作品:「ある脅迫」(1960年/日活/65分/監督:蔵原惟繕、出演:金子信雄、西村晃)
*ニュープリント、英語字幕付き
同じ銀行で働く、やり手の銀行員・滝田と小心な庶務係・中池とは幼なじみ。栄転が決まった滝田は、ヤクザから強請られ、銀行強盗を企てる。その時、中池は……。直木賞を受賞した多岐川恭の短編ミステリーを原作に、心理サスペンスを濃密に描くフィルム・ノワール作品。"SP(シスター・ピクチャー)"と呼ばれる二本立興行用の中篇として撮られた。後に監督となり喜劇映画で活躍する瀬川昌治が、ペンネームで脚本を執筆している。
○募集人数:25組50名
○応募方法:メールによる申込
・メール件名を「10/7『ある脅迫』試写会応募」として、メール本文に(1)お名前、(2)メールアドレス、(3)郵便番号・住所、(4)お電話番号を明記の上、present@filmex.jpまでお申し込みください。
(締切:2008年10月3日(金)24:00)
*当選者へはメールにてご連絡いたします。

(C)1960 NIKKATSU Corporation.All rights reserved.
「幸福 Shiawase」が劇場公開されています。
2006年の第7回東京フィルメックスで上映された、小林政広監督の「幸福 Shiawase」が9月20日からシネマート六本木で公開されています。
撮影は3年前でやっと劇場公開が決まったこの作品。北海道・苫小牧を舞台に、心にしみるラブ・ストーリーを是非劇場でご覧下さい。
第7回フィルメックス舞台挨拶
第7回フィルメックス舞台挨拶動画
第43回カルロビバリ国際映画祭 報告
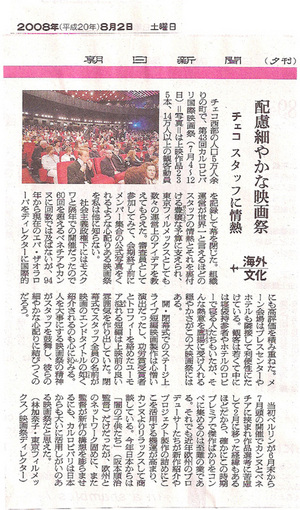
配慮細やかな映画祭
チェコ スタッフに情熱
チェコ西部の人口5万人余りの町で、第43回カルロビバリ国際映画祭(7月4~12日)は上映作品235本,14万人以上の観客動員を記録して幕を閉じた。組織運営が世界一と言えるほどのスタッフの情熱とそれを裏付ける豊穣な予算に支えられ、東京フィルメックスとしても数々の運営上のアイデアを教えてもらえた。審査員として参加してみて、会期終了前にメンバー集合の公式写真をくれるような心配りある映画祭を私は他に知らない。
社会主義政権下にはモスクワと隔年での開催だったので60回を超えるベネチアやカンヌに回数では及ばないが、94年から現在のエバ・ザオラローバをディレクターに国際的にも高評価を積み重ねた。メーン会場はプレスセンターやホテルも隣接して利便性にたけている。観客は若くて中には寝袋持参者やホテルのロビーで寝る人たちもいたが、そんな熱意を鷹揚に受け入れる穏やかさがこの大映画祭にはある。
開・閉幕式でのステージ上ライブ短編映画製作は心憎い演出だったし、功労賞受賞者とトロフィーを絡めたユーモア溢れる短編は上映前の良い雰囲気を作り出していた。閉幕式でスタッフ全員の名前が映画のエンドタイトルの如く紹介されるのも心に沁みる。人を大事にする映画祭の精神がスタッフを鼓舞し、彼らの細やかな心配りに結びつくのだろう。
当初ベルリンが6月末から7月頭の開催でカンヌとべネチアに挟まれ作品選考に苦慮して2月に移った経緯もあるほどだから、確かにこの時期プレミアで傑作ばかりをコンペに集めるのは至難の業である。それでも近年欧州のプロデューサーたちが新作紹介やプロジェクト製作の詰めにここを活用する機運が高まり、カンヌよりリラックスして商談している。今年日本からは「闇の子供たち」(阪本順治監督)だけだったが、欧州とのネットワーク固めに、また監督が新作の構想を膨らませるにも、カルロビバリは日本からも大いに活用しがいのある映画祭だと思えた。
東京フィルメックス/映画祭ディレクター,林 加奈子
(2008年8月2日 朝日新聞夕刊より転載)
第61回カンヌ国際映画祭レポート

今年のカンヌ国際映画祭で公式上映された日本映画は『トウキョウソナタ』のみだったが、ある視点部門審査員賞を受賞して存在感を示した。また、日本人俳優が出演し東京で撮影された『TOKYO!』も注目を集めた。これらは従来の枠組を越える新たな軌跡を描いて誕生し、今後の日本映画の可能性を予感させるものとなった。(東京フィルメックス事務局・森宗厚子)
5月15日に上映された『TOKYO!』は日・仏・韓・独の合作による3部作。監督・脚本は、ニューヨークからミシェル・ゴンドリー(『恋愛睡眠のすすめ』)、フランスからレオス・カラックス(『ポーラX』)、韓国からポン・ジュノ(『グエムル-漢江の怪物-』)が参加し、俳優とスタッフはほぼ日本勢という布陣で作られた。
ユニークな視点から東京を舞台にし、馴染みある俳優達やありふれた都市風景を被写体としながら、見過ごされていた異なる魅力や東京の本質を描き出し、新鮮な驚きをもたらす。フランス在住の日本人プロデューサーを中心に製作されたが、外国の資本や才能との協働により、日本の環境の中で生み出される映画のバリエーションを広げている。
そして5月17日、『トウキョウソナタ』は大きな拍手によって迎えられた。1997年『カリスマ』が監督週間で上映されて以来、2001年『回路』がある視点、03年『アカルイミライ』がコンペで、とカンヌで度々紹介されている黒沢清監督だが、今回は「びっくりするくらい反応が良かった」と手応えを記者会見で語った。監督の新境地ともいえる家族のドラマは、世界に通じる普遍性を持ち高く評価された。「この作品が最後に与えるのは映画を見たというよりも、醜さ、恐ろしさ、そして素晴らしさと驚きを全て含むひとつの人生を生き抜いたという感情だ」(シネマティカル)という絶賛評もある。
また、作品の成立過程も新しい展開を示している。外国との共同製作によるものだが、オーストラリア出身のマックス・マニックスが書いた脚本に興味を持った木藤幸江プロデューサーが、共同製作のパートナーとして、オランダや香港などを拠点に製作/国際セールスを手がける会社フォルティシモのバウター・バレンドレクトと組み、黒沢監督に声をかけたという経緯がある。
初期段階で木藤プロデューサーは、経済産業省と日本映画の国際振興を担う組織ユニジャパンの主催による共同製作支援プログラム<J-Pitch>に参加して、2006年にカンヌでの企画ピッチングを行ない、スムーズに製作に取り掛かった。そして、2年を経て完成した作品を公式上映で披露し、受賞して作品的に評価されるとともに、ビジネス的にもすでに世界11カ国以上での配給が決まるなど成果を挙げている。
木藤プロデューサーは、以前より外国映画の共同製作に携わっていたが、日本映画を初めて手がけるにあたり<J-Pitch>のバックアップが「大変ありがたかった」と語る。折しも2006年に始動した<J-Pitch>は改良を重ねつつ、ロッテルダム、ベルリン、香港、プサンなど主要映画祭の企画マーケットとの提携や脚本などの翻訳サポートといった実践的な支援体制を整えてきている。『トウキョウソナタ』をはじめとする実績を内外へのアピールとして、継続的な取り組みにより今後のさらなる展開が期待される。
日本映画界は特殊性が高いとされ、他国に比べて共同製作がまだまだ活性化していないが、<J-Pitch>など公的支援により内外の映画界の橋渡しとなる効果的なプラットホームの整備が望まれている。
※『TOKYO!』晩夏、シネマライズ、シネリーブル池袋他全国公開予定(配給:ビターズ・エンド)
※『トウキョウソナタ』秋、恵比寿ガーデンシネマ他全国公開予定(配給:ピックス)
以上
(報告者:森宗 厚子)
*公明新聞 2008年6月6日(金) 掲載記事より転載

