11月30日(土)、東京フィルメックス授賞式が有楽町朝日ホールにて行われ、たくさんの人が押しかけた。

5人の審査委員から、映画批評家のトニー・レインズ、俳優のべーナズ・ジャファリ、写真家の操上和美が式に出席。俳優のサマル・イェスリャーモワ、深田晃司監督はスケジュールの都合で欠席となった。コンペティションで上映された10作品の中から、学生審査員賞、スペシャル・メンション、審査員特別賞、最優秀作品賞受賞作品が発表された。

その前に、クロージング作品以降に上映される作品を除いた全プログラムから、観客賞に中川龍太郎監督の『静かな雨』が選ばれた。
代理で藤村プロデューサーが賞状を受け取り、中川監督からはビデオメッセージが届いた。
<中川龍太郎監督 ビデオメッセージ全文>
『静かな雨』監督の中川龍太郎です。学生時代から友人としょっちゅう通っていた映画祭で、観客賞というすばらしい賞を頂けて本当にうれしく思っています。何度もなんども行っていた映画祭ですので、そのときに一緒に見ていたお客さまからのご支持を少しでもいただけたのだとしたら、こんなに光栄なことはございません。
この映画は2月7日に、劇場公開されます。そのときはまた見ていただけたらうれしいです。今回はありがとうございました。

学生審査員賞は、ニアン・カヴィッチ監督の『昨夜、あなたが微笑んでいた』に贈られた。カヴィッチ監督本人が登壇し、賞状を受け取った。
<ニアン・カヴィッチ監督 受賞コメント全文>
学生審査員の皆さん、ありがとうございました。そして、2016年に自分を(タレンツに)選んでくださったタレンツ・トーキョーにも、あらためてお礼を申し上げたいです。今度は自分の作品を持って、東京フィルメックスにこうやって戻ってこられたことを大変光栄に思っています。本当にありがとうございました。
スペシャル・メンションは二つの作品に授与された。

一つめの作品は、広瀬奈々子監督の『つつんで、ひらいて』。昨年も『夜明け』(18)で同賞を受賞した広瀬監督本人が、賞状を受け取った。
<広瀬奈々子監督 受賞コメント全文>
昨年、スペシャル・メンションを頂いたばかりだったので、今年もこの場に立てるとはまったく思っていませんでした。市山さんにも、最初に「今年は賞とかは期待しないでください」と言われていたので、びっくりしています(笑)
お聞かせいただいた授賞理由の批評が本当にうれしくて、感動しております。装丁というジャンルの表現にこうして光をあててもらえるというのが、何よりうれしいです。本が売れない時代に紙の本について考え直すのは意義があると感じているので、一人でも多くの人に届いてくれたらいいなと思います。本日はありがとうございました。

二つめの作品は、ニアン・カヴィッチ監督の『昨夜、あなたが微笑んでいた』。学生審査員賞とのダブル受賞という結果になったカヴィッチ監督が、再び舞台上にあらわれた。
<ニアン・カヴィッチ 受賞コメント>
また戻ってきました(笑) まずは審査員の方々にお礼を申し上げたいです。本当に光栄に感じています。
ちょっと思い出したんですが、タレンツ・トーキョーに参加したときに、フライトに乗り損ねるというヘマをやらかしてしまいました。けれどもタレンツ・トーキョーさんが、もう一回チャンスをくださったんです。そして、作品を作り終え、皆さんにお見せすることができて、その上このような賞を頂けて、大変うれしく思っています。
この先はあまりそういう失敗はしないようにしたいです。ありがとうございました。

審査員特別賞は、グー・シャオガン監督の『春江水暖』。
代理で友人が賞状を受け取り、シャオガン監督からは時おり日本語を交えたビデオメッセージが届いた。
<グー・シャオガン ビデオメッセージ全文>
みなさん、こんにちは。私は『春江水暖』の監督のグー・シャオガンです。
あのう、すみません。スケジュールの都合で、会場で賞を受け取れなくてごめんなさい。審査員の皆さんが、この作品に賞を与えてくれると知ったときは、とても光栄でうれしく思いました。
まずは、出資会社に感謝を申し上げます。
この映画のエグゼクティブ・プロデューサーのリー・ジャーさんに感謝します。
プロデューサーのホアン・シューホンさん、そしてすべての制作チームに感謝します。
それから、私の家族に感謝します。
それと、この映画をサポートしてくれたすべての人に感謝します。
撮影スタッフの一人ひとりには、とびきりの感謝を伝えたいです。春夏秋冬の季節を一緒に歩んでくれて、どうもありがとう。私たちは力を合わせて、この映画を完成させました。みんながいなかったら、この映画も存在しなかったでしょう。だから、みんなに感謝します。
僭越ですが、私がスタッフと映画を代表して、東京フィルメックスの審査員の皆さま方に感謝を申し上げます。私たちの映画を激励し、認めてくれてありがとうございます。最後に、市山さんにも感謝します。
この映画を日本に連れてきてくれて、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。

そして栄えある最優秀作品賞には、ペマツェテン監督の『気球』が輝いた。ペマツェテン監督は、これまで2度『オールド・ドッグ』(11)、『タルロ』(15)で本映画祭同賞を受賞。
主演のジンパが、ペマツェテン監督からのメッセージを代読した。
<ペマツェテン 受賞コメント全文>
こんばんは。東京フィルメックスに出品するたびに、このように賞を受賞することができるとは思ってもいませんでした。本当に、ご縁としか言いようがありません。映画祭に参加するたび、私はこの上ない感謝の気持ちを覚えております。
映画祭の組織委員会の皆さんには、私の最新作『気球』を日本に連れてきてくださり、そして熱心な日本の観客に届けてくださいましたこと、ありがたく思っております。
審査員の皆さん、この映画に大きな栄誉を与えてくださいましたこと、感謝しております。
最後に、皆さんに吉祥あれ。

最後に、トニー・レインズ審査委員長が講評を述べた。多様性に富んだラインナップに一つ共通点があるとすれば、本映画祭ディレクター・市山尚三の選択眼が特異なものだったと10作品を振り返る。多くの映画祭で審査員を務めるレインズだが、これほどまでにすべての作品が同じレベルに到達していることはまれだという。審査員団についても、多種多様な5人で「いいミックスだった」と述べた。
最優秀賞受賞作品は満場一致で決まったそうだ。「受賞暦がない人のほうがいいかもと考えましたが、『気球』のクオリティに強い説得力を感じ、“やはり……”となりました」

大きな拍手が鳴り響くなか、2019年、第20回東京フィルメックス授賞式は幕を閉じた。
続けて、受賞者記者会見がスクエアBにて開かれた。

カヴィッチ監督へ、「タレンツ・トーキョーで得たことは?」という質問が挙がる。カヴィッチ監督は、「参加者たちと直接顔を合わせなくても、連絡をとって作品の状況を話し合える関係が続いているのがすばらしい。チャンスをくださって、キャリアに大きく役立ちました」と答えた。また、「フィクション作品が上がったところ」と、次回作についても言及していた。

キャリアでフィクションとドキュメンタリーを1本ずつ手がけたことになる、広瀬監督。「今後の方向性は?」と聞かれ、「メインのフィールドとしては、フィクションをやっていきたいですドキュメンタリーには相当な忍耐力と時間が必要になる。本作では菊地信義さんとのすばらしい出会いがあったので追いかけられましたが、それだけの人にめぐり合える機会もそんなにありません」と答えた。

さらに、審査委員へ、「最優秀賞は全員一致だったそうだが、その他の賞の審査は難航したのか?」と質問が投げかけられた。
レインズ審査員長は、「審査員室の秘密は外に出してはいけないので、お話するのが難しい」と言いつつ、『春江水暖』は審査員のうち5人中4人がセカンド・チョイスに選んでいたと明かした。もう1人もディスカッションの末に、『春江水暖』を推したそう。
またレインズによれば、スペシャル・メンションには当初4本が候補に挙がったが、審査員同士で意見がぶつかったというより、「それぞれにお気に入りがあった」のだとか。「われわれは大人の会話をし、矜持を持って、リーズナブルな見解を生みました」とまとめた。

ジャファリは、審査はとても穏やかな話し合いだったという。「いろんな国の映画を見て、世界を一周したみたいです」とも。「でも共通するテーマは、やはり“神さま”でしょうか。こういう機会を頂くと、人間を知ることができますね」と、映画祭を通して考えたことを語った。

操上は、「価値観や文化的背景など、異なる出自の人たちが作った映画を、自分が審査するということは簡単ではない」と悩んだそう。「なるべく個人の好き嫌いは抑え、“映画としてどうか”を心がけて見て、こういう審査結果になりました」。そして、「あらためて、すばらしい作品をありがとうございました」と挨拶をした。

文・樺沢優希/写真・明田川志保、白畑留美
































































 さらに、2人の俳優が演じた水産工場で働く若者の過酷な労働環境について話が及ぶと、パク監督は、実は船乗りだった時期があり、劇中の若者たちと同様に水槽タンクで寝かされ、労働搾取を感じたというエピソードを披露。道徳的不感症の被害者として、当時の記憶を本作に盛り込んだという。
さらに、2人の俳優が演じた水産工場で働く若者の過酷な労働環境について話が及ぶと、パク監督は、実は船乗りだった時期があり、劇中の若者たちと同様に水槽タンクで寝かされ、労働搾取を感じたというエピソードを披露。道徳的不感症の被害者として、当時の記憶を本作に盛り込んだという。





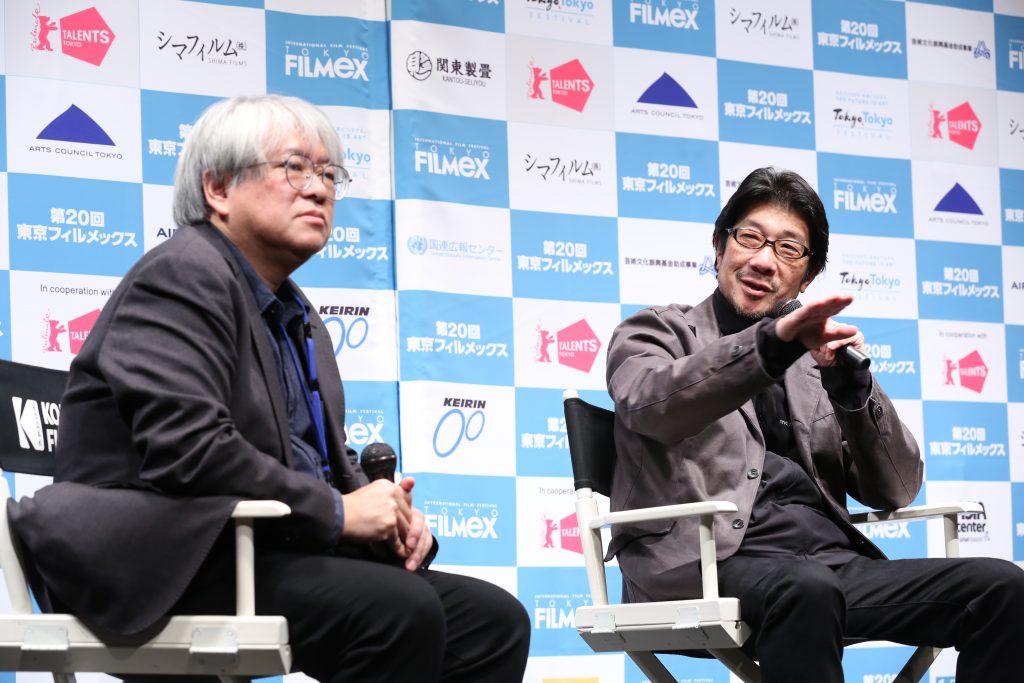

 とはいえ、「今後、大阪を舞台に映画を撮ってみたいか」との質問に対しては「あの場所がもうかなわないとすれば、どこかもっと面白い場所があると思うので、土地柄やそこに暮らす人たちに興味を持てば、そこでしか成り立たないものをまた考えたい」と意欲を見せた。
とはいえ、「今後、大阪を舞台に映画を撮ってみたいか」との質問に対しては「あの場所がもうかなわないとすれば、どこかもっと面白い場所があると思うので、土地柄やそこに暮らす人たちに興味を持てば、そこでしか成り立たないものをまた考えたい」と意欲を見せた。