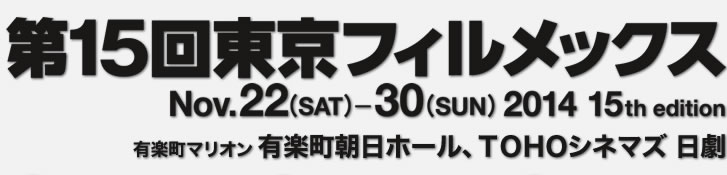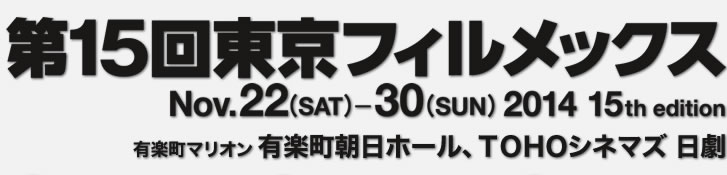スクエアイベント「クローネンバーグについて」(ゲスト:篠崎誠監督、柳下毅一郎さん)
TOKYO FILMeX (2014年11月29日 15:30)

11月29日、有楽町朝日ホールにて特別招待作品『マップ・トゥ・ザ・スターズ』の上映が行われた。本作は日本でも熱狂的なファンを多くもつデヴィッド・クローネンバーグ監督の最新作。また、同監督の学生時代に自主製作した2本『ステレオ/均衡の遺失』(1969)、『クライム・オブ・ザ・フューチャー/未来犯罪の確立』(1970)の特集上映も合わせて行われた。上映の間には朝日ホール11階スクエアにて、映画監督の篠崎誠さんと映画評論家の柳下毅一郎さんをゲストに迎え「クローネンバーグについて」と題したイベントを開催し、クローネンバーグ監督作品の魅力について縦横無尽に語ってもらった。
まず、市山尚三東京フィルメックス・プログラムディレクターから、特集上映される2作品について「ともにDVD化されておらず、観る機会が少ない作品」と紹介された。
『ステレオ』をはじめて観たときの印象について柳下さんは「既に特殊メイクホラーの監督というイメージが確立されてからの公開だったため、最初は地味な印象を受けた。しかし、特殊メイクの使用が目立たなくなった最近の作品群と比較すると、素直にその類似性がみてとれる」と語った。篠崎監督もそれに同意し「監督は処女作に向かって成熟するといわれるが、まさにそう。後のクローネンバーグ的なテーマが既に現れていて、夢と現実、形と動き、精神と肉体を対立させて描くのではなく、どこかで交じり合わせるような印象がある」「最新作でも登場するボブカットの女性が初期作からみられるのも興味深い」とコメントした。

また、篠崎監督は初期2作の特徴としてクローネンバーグ自身が撮影をしていることを挙げ「他の作品にみられるオーソドックスな画作りと違い、フレーミングが独特。実相寺昭雄監督を思わせる空間を強調したような撮り方をしている」と語った。それに対し市山PDも実相寺監督のウルトラマンセブン第43話『第四惑星の悪夢』を想起したと述べ、柳下さんからも「無機質なコンクリート打ちっぱなしの建物が舞台のSFドラマとして、当時の時代的なものを感じる。ディティールは『アルファビル』(65)を想起させられる」と作品の背景が語られた。
近年の日本映画では同系統の映画があまりみられないとの声に、市山PDから「ここに一人います」と篠崎監督をゲストに迎えた理由が明かされた。今年のフィルメックスの特別招待作品でもある『SHARING』をバンクーバー映画祭のプログラマーであるトニー・レインズさんにみせたところ、低予算で大学内で撮影されていて、SF的な作りという点で『クライム・オブ・ザ・フューチャー』を想起したとのこと。今年のフィルメックスで同時に上映される偶然に驚いていたそうだ。
次に篠崎監督は、ある時期までのクローネンバーグ監督の物語を語りながら解体しているような作風について「ヤンチョー・ミクロ―シュ監督の作品やジョナス・メカスをはじめとしたニューヨークのアンダーグラウンドと通じているような印象がある」と語った。また柳下さんも「ストーリー上関係ないショットも撮っておいて、それにアフレコをいれたり、編集で自由につないでいる印象がある」とアート映画からの影響について言及した。しかし一方で「もともとクローネンバーグは作家志望で、英文学を専攻していた。そこで、ウィリアム・S・バロウズの影響から自由になれず悩んでる時期に、映画と出会った。結果、特殊メイクホラーの分野で才能が開花したが、本来の思考は『ステレオ』や『スパイダー/少年は蜘蛛にキスをする』(02)によく表れており、シネフィル的な映画愛に根差したものではない」とコメントし、小説の表現を熟知した上で、映画というメディアの独自性に至った過程を説明した。
次に、クローネンバーグ監督作品に一貫してみられるセクシャルポリティクスとアイデンティティについて話が及んだ。篠崎監督は「『スパイダー』では、過去と現在、夢と現実が絶えず対照的にあるのでなく、両方があってはじめて成り立っている。とてもクリアでグロテスクなので、どちらが夢かわからないというような撮り方を絶えずしている」と自己同一性における自己そのものがあやふやに描かれる点についてコメントした。それに対して柳下さんは「単純な自分探しという意味だけでなく、映画とSFとアイデンティティの問題で考えると、フィリップ・K・ディック的な、"本当の自分がどこかにいること"を前提としたアイデンティティ不安はよく扱われるが、クローネンバーグにおいては、周囲との関係性まで含めて自分であるような意識が独特だ」とコメントした。またその具体例として『スキャナーズ』(81)におけるスキャナー(テレパシー能力)で他人の意識が自意識に流れ込む設定や、『ヴィデオドローム』(83)における幻覚の主観描写、『ステレオ』におけるテレパシーの発動条件をあげ、あふれ出てくる自分や他人や幻想の領域についての問題がクローネンバーグ監督には一貫して付きまとっていると説明した。
その意見に篠崎監督も同意し、作中で兄弟や双子がよく扱われる点を指摘した上で「『スパイダー』では本当の過去か捏造された過去かわからない地点に、少年の自分と成人した自分が同じフレームにいる。『デッドゾーン』(83)も、他人の運命の中に自分が入り込む。そういう意味で主観・客観ショットという概念さえも意図的に混じりあい、客観映像の中に本人もいて、それでありつつそれが主観であるような撮り方をしている点が面白い」とコメントした。

続いて、クローネンバーグ監督が描く登場人物の服装について話が及んだ。柳下さんは『スパイダー』のレイフ・ファインズがシャツを重ね着していることに注目し「必死で幻想を抑え込んでいる」と語った。篠崎監督は『ザ・フライ』(86)のジェフ・ゴールドブラグが、同じ服を五つ持っていることについて「放っておくと世界に飲み込まれそうになるので、自分を律して、余計なことをしないようようにしているようだ」とコメントした。
また、クローネンバーグ監督自身の性格について柳下さんから「精神分析は受けたことありますかと聞かれて、私は理性的すぎるから分析医を分析しちゃう、と答えるような人」といったエピソードが語られる一方、篠崎監督からは「離婚訴訟中に撮影していた『ザ・ブルード 怒りのメタファー』(81)で、妻役のサマンサ・エッガーの首を絞めるシーンにカタルシスを感じたという話を聞いた。そういった暗黒面を、あまり表側には出さない」とその印象を語った。また、『ステレオ』での性の描かれ方を例にあげ「それは愛のないセックスと言われがちだが、この映画で印象に残ったのは「愛はすべてに打ち勝つ」というセリフです。それは反語的に言っているのではなく、どこか本気で考えていると思う。そうでないと『デッドゾーン』(83)や『ザ・フライ』のような映画はとれない。ただ、その愛はハリウッド的な分かりやすい形で表現されるわけではなく、愛っていうのは確かにあったけれども、それが分かった時点でどちらかが死ななくてはいけない。『スキャナーズ』や『エム・バタフライ』(93)で二つの対立する概念を自分の中に取り込んでいくシーンによく表れている」と分析した。
次に、クローネンバーグ監督作品の多くで「人が衆人環視のもとで死んでいる」という特徴があげられた。篠崎監督は『スキャナーズ』『ザ・ブルード』『デッドゾーン』『エム・バタフライ』『クラッシュ』(96)を例にあげ「何か決定的な出来事が起こる瞬間には必ず、関係ない他人の何重もの視線を受け止めている」とコメント。それに対し柳下さんは「事件というのは目撃されないと事件にならない。初期のクローネンバーグは可視化に憑りつかれていて、特殊メイクを多用していた」と語った。それを受け篠崎さんからは「『ザ・ブルード』の託児所での殺害において、隠しカメラで撮っている子供が本当にショックなリアクションをとっていて、ひどいことをする人だなと(笑)」と事件性を演出する際のエピソードが紹介された。
また篠崎監督は『デッドゾーン』と『ザ・フライ』のラストのフレーミングが同様である点や、『ステレオ』と『クライム・オブ・ザ・フューチャー』のモチーフが対になっている点に注目し「作品同士が離れた双子のように共鳴していてる」とコメント。クローネンバーグ監督の初期作品のカメラマンであるマーク・アーウィンも「クローネンバーグの映画は全部相対で観たときに何かが見える」と語っていたそうで、全作品が壮大なタペストリーのようになっているようだ。
長編第二作の『クライム・オブ・ザフューチャー』について、柳下さんはホモセクシャルをモチーフとして描いている点に注目し「性の問題は、その後の作品にもずっと底流として流れてる。単純なホモセクシャルやヘテロセクシャルではなく、全ての対象がセックスの対象となるような思考で、セックス自体も解体してるようなところがある」とコメントした。
最新作の『マップ・トゥ・ザ・スターズ』について、篠崎監督は「出だしは、デヴィット・リンチの近作に似ていると思った」と印象を語った。それを受け市山PDは「カンヌでやったときは『マルホランド・ドライブ』(01)のクローネンバーグ版だと言われた」と紹介した。柳下さんからは「ストーリー的には原作者が持ってるモチーフ。クローネンバーグ的なテーマではない。ハリウッドが舞台として描かれるが、リンチと違い、ハリウッドバビロン的なものに対する思い入れはなさそうだ」と語った。また、クローネンバーグがはじめてトロントを離れて撮った点を指摘し、今までのセットとは違う建築の面白さを指摘した。
ここで、ゲストの2人がクローネンバーグ監督の中でオススメしたい作品を紹介した。篠崎監督は、代表作という意味でなら『ヴィデオドローム』『スキャナーズ』だが、一番自分の中で響くのは『デッドゾーン』『戦慄の絆』『クラッシュ』だと語った。何かのイデオロギーにもたれかかったりしないで、人間が孤立して、肉体や愛が消えて行ったり、モノになって終わるラストに寂しくなるが感動するとのこと。
柳下さんは思い入れのある『クラッシュ』と『ザ・ブルード』が好きなのだそう。
最後に、クローネンバーグがみた夢について。撮影中にこんな夢をみたそうだ。「僕は巨大なかまきりになっていて、砂漠で自分の手を食べている。食べては吐き出しを繰り返していると、すごい砂嵐がきて、吐き出したものが全部裸の自分になって倒れていた」。篠崎監督は「このように非常にユニークなビジョンを持っているが、映画の中でそこまで狂った夢のイメージは出てこない。夢のビジョンについて、禁欲的な意識があるのでは...」と、お二人ともまだまだ話は尽きなかったが、ここで時間終了。
会場は多くの立ち見が出るなど、熱気に溢れていた。そんな中ゲスト二人のディープな話が繰り広げられ、クローネンバーグ監督の映画を観たときのような濃密でスリリングな時間を体感したトークショーだった。最新作『マップ・トゥ・ザ・スターズ』は12月20日(土)より新宿武蔵野館ほか全国ロードショーされる。
(取材・文:高橋直也、撮影:穴田香織)
  

|