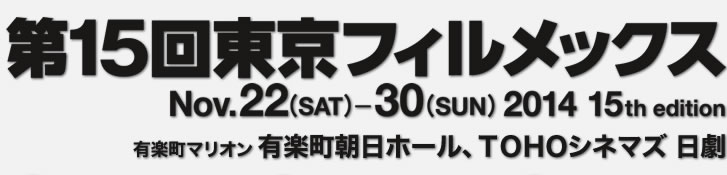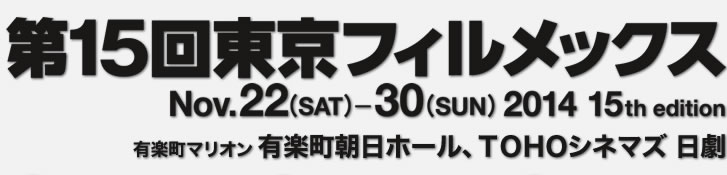『ディーブ』ナジ・アブヌワール監督、ナセル・カラジ プロデューサーQ&A
TOKYO FILMeX (2014年11月27日 17:30)

11月27日、有楽町朝日ホールにてコンペティション部門の『ディーブ』が上映された。本作は、遊牧民ベドウィンの少年ディーブの目を通して、第一次世界大戦中にオスマン帝国支配下にあったアラビア半島の情景が描かれており、東京フィルメックスで初めて紹介されたヨルダン作品である。上映後のQ&Aには、ナジ・アブヌワール監督とプロデューサーのナセル・カラジさんが登壇し、熱心な観客たちから質問が相次いだ。
まず、アブヌワール監督が「まさか日本のお客さんに観ていただけるとは思っていなかったので、この機会をとても嬉しく思っています」と述べ、またカラジさんは「私どもは日本と映画と文化に敬意を抱いています。みなさんからのフィードバックを楽しみにしています」と挨拶した。
続いて、市山尚三東京フィルメックス・プログラムディレクターが、長編デビュー作にベドウィン族を題材として選んだ理由を尋ねた。アブヌワール監督は、以前からベドウィン文化に魅せられ、映画制作を始めた頃からこの題材を取り上げたいと思っていて、ストーリーを作り上げるまで10年ぐらいかかったそうだ。

会場からキャスティングについて問われると、英国人役以外の登場人物は全員アマチュアで、1990年代までヨルダンで遊牧活動をしていた部族から起用したことを明かしたアブヌワール監督。とくに主人公の少年ディーブ役を演じたジャーサル・イードさんについては、ベドウィン側の製作担当者に少年役を見つけるように依頼したところ、その担当者はよくよく探しもせずに自分の息子を送り込んできたそうだが、いざ撮影に入るとスクリーンで輝くような存在だったため、キャスティングには満足したそうだ。
次に、劇中登場する鉄道が意味するものについて話が及んだ。アブヌワール監督は、鉄道の開通を「部族間の紛争や第一次世界大戦を含めたその後に続くアラブの暗い時代の始まり」であり「ヨルダンにおけるベドウィン文化の終焉の前兆」と位置付けた。というのも、オスマン帝国による鉄道敷設は、メッカまでの巡礼者たちのガイドや用心棒で生計を立てていたベドウィンの人々の生業を奪う結果になったからだ。

さらに、本作の製作国のクレジットはヨルダン、英国、UAE、カタールと多国籍にまたがっている。製作国が多いのは低予算映画であるがゆえで、あちこちから投資を集める必要があったからだという。ポストプロダクションの費用はUAEとカタールの会社から、製作費の一部は英国の製作会社から出資だが、大半はヨルダンからの出資とのこと。また、中東に混乱を撒いた張本人は英国ではないかという指摘を受けると、英国人とヨルダン人の間に生まれたアブヌワール監督は、英国とヨルダンの両方の文化を背負っていると自負しながらも、本作が歴史的・政治的背景を勉強するためのものではないことを強調。さらにカラジさんは、「英国が歴史的に中東に大きな影響を与えてきたのも確かだが、むしろオスマン帝国が社会の腐敗や分裂に貢献したところがあり、オスマン帝国の傷痕はいまだに残っていると思います」と付け加えた。
さて、本作の魅力のひとつはヨルダンの壮大な砂漠地帯の風景であるが、撮影での苦労話をうかがうことになった。アブヌワール監督によると、撮影中に砂漠で迷子になったり砂に埋まって動けなくなったりしたこともあったそうで、そのたびにベドウィンの人たちに助けてもらったとか。また、砂漠の奥地で撮影したため、照明機材や発電機など重機材の持ち込みに制約があったことも。ただし、アマチュアの役者のリアルな演技をその場でそのまま撮影する手法をとっていたので、クレーンなどの重機材が使えなくても芸術映画としてはマイナスではなかったと、アブヌワール監督は振り返った。
また、劇中で語られた「男の生きる道」について問われると、アブヌワール監督は「ベドウィンの美学は、"困難の中でも生き残る"ということだ」と説明。それは、砂漠の中で食糧を求めて狩猟を行い、水を見つけることができるということ。現在は定住生活へ移行したため、ベドウィンの男たちは近代化の中で方向性や価値観を喪失してしまっており、そうした状況は悲しいことだとアブヌワール監督は語った。
最後の質問は、シネマスコープを意識した演出の素晴らしさを称えた観客から、撮影監督にヴォルフガング・ターラー氏を迎えた経緯について。アブヌワール監督が探し求めていた撮影監督の要件はとても厳しいもので、その要件とは、辺鄙な場所での撮影経験があること、充分な機材が備わっていなくてもスケールの大きな画を撮れること、外国の文化に対して敬意を払い人間的な付き合いができること、そして、本作ではスーパー16mmにアナモルフィックレンズを使用するためフィルムを扱う経験値が高いことの4点。ターラー氏は、ウルリヒ・ザイドル監督作品でアマチュアの役者と仕事をすることに慣れており、また、ミハエル・グラウガー監督などトップクラスのドキュメンタリー製作に関与し世界中でロケを経験していることから、総合的に判断してターラー氏のほかに考えられなかったそうだ。
ここで惜しまれつつQ&Aが終了し、会場からは盛大な拍手が送られた。Q&A後には、会場の外でアブヌワール監督に質問や感想を寄せる観客たちが続々と集まり、本作への関心の高さがうかがわれた。アブヌワール監督のさらなる飛躍に期待したい。
(取材・文:海野由子、撮影:白畑留美)
  

|