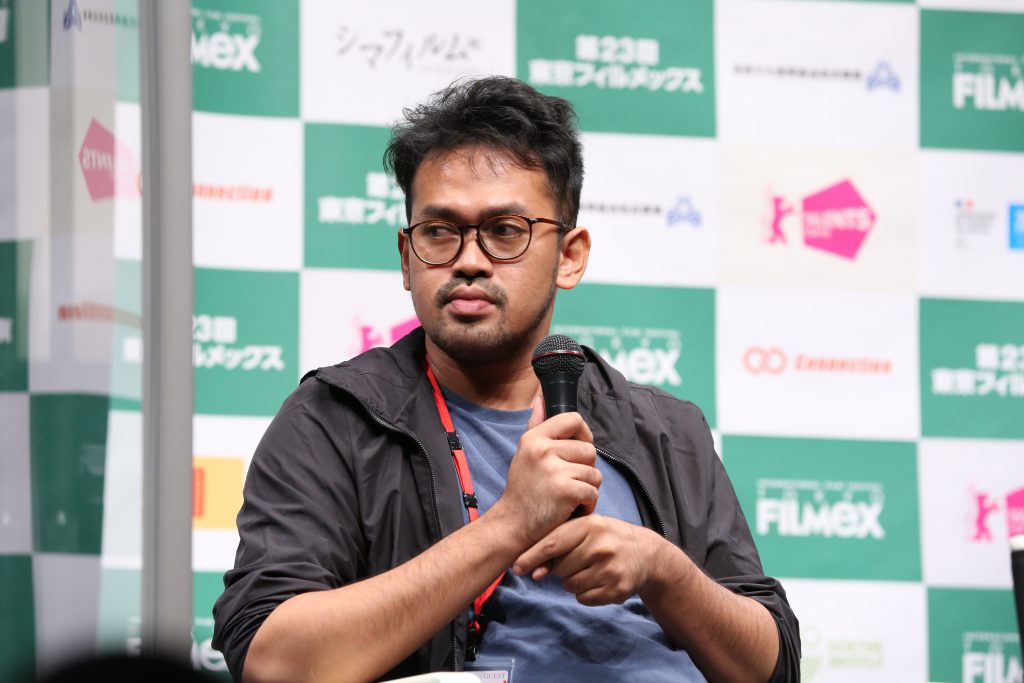11月5日(土)、クロージング作品の『すべては大丈夫』が有楽町朝日ホールで上映され、コンペティション部門の審査委員長も務めたリティ・パン監督が上映後の質疑応答に登壇した。自ら手作りした粘土人形と様々な映像を組み合わせて、動物が人間を支配するディストピアを描くシネマエッセイ。作品に込めた寓意や製作の経緯をパン監督が縦横に語った。

粘土人形を駆使した作品は、祖国カンボジアのクメール・ルージュによる圧政の記憶を描いた『消えた画 クメール・ルージュの真実』(2013年)以来。フランス在住のパン監督は、コロナ禍のロックダウン中にこの企画を思い付き、書斎をスタジオ代わりに製作に取り組んだという。「最初のロックダウンの時、空っぽになった街に動物が入り込んでいるのを目撃し、クメール・ルージュがカンボジアの人々を追い出した時のことを思い出した」とパン監督。感染対策で始まったはずの規制や検査が、次第に本来の目的を超えて人々をコントロールしているようにも感じ、全体主義の台頭をめぐる寓話につながった。
豚が率いる動物の一群が人間社会を征服する。自由の女神像が倒され、代わりにスマートフォンを掲げた豚の像が建立される。「豚をリーダーにした理由はふたつある」とパン監督。「まず、ロックダウン当時の米国大統領だったドナルド・トランプのことを考えました。四六時中流れてくるトランプのツイートは、まるで世界をコントロールしようとしているかのように思えました」。一方で、豚は賢い動物で、ヒトに近い面もあるという。「豚と人間には互換性があるんです。私たちが皮膚移植する際も豚の皮膚を使う。失敗に終わったが、数カ月前には豚から人間への心臓移植手術もあった。いずれは実用可能になるかもしれません」

では、動物たちが自分を人間に似せようとしたらどうなるか。「人間のような5本指を持ちたいと願い、人間の行動を模倣した動物たちは、やがて全体主義へと行きつく。そのプロセスを寓話として描いたのが今回の作品です」とパン監督。「新型コロナウイルスはどこから来たのかを考えてみて下さい。人間が森を破壊し、そこに住んでいた動物たちが否応なしに街に出て来る。そしてウイルスが広まり、今度は人間たちがロックダウンで閉じ込められる。そういう現象を映画にしようと思ったのです」
動物が支配する社会はあちこちにスクリーンが設置され、過去の戦争や虐殺や独裁者の映像が流れる。そこに警句的なテキストの朗読が重なる。「こんなキツい映画に最後までお付き合いいただき感謝します。こういう映画は全てを理解する必要はないんです。例えばワンシークエンスだけでも何か気になったことを考えて下さったら本当にうれしい」

客席からは、多彩なアーカイブ映像の使い方について質問があった。「建物の管理人が監視カメラを眺める姿をイメージしました。人工衛星、スマホ、顔認証技術。様々なものが我々を監視し、コントロールしている。そんな全体主義的状況を映画にしました」とパン監督。一方で、ロックダウン期間に見直した映画史上の作品群のイメージも生かされているという。「ジガ・ヴェルトフやフリッツ・ラングの映画の要素がピンク・フロイドの『ウォール』のビデオに生かされているように、アーティストは互いを模倣しあっています。私もこれはいいと思った他の監督の作品をピックアップしている。もちろんそのままコピーするわけではなく、別の表現方法で。芸術には真の意味でのオリジナルなど無い。私は自分を『イメージの盗っ人』と呼んでいます」

共同脚本を手掛けたのは作家クリストフ・バタイユ。「彼とのコラボは3、4作目になるかな。『この映像に言葉を足して』って頼むと、言葉の自動販売機みたいに足してくれるんです。そのまま映像に当てはめるのではなく、別の場面と組み合わせることもある。決まりごとはありません」。音楽は『消えた画』や『名前のない墓』でも組んだマルク・マルデル。「彼も30年以上一緒にやっているので、様々なサウンドを彼の方から提案してくれる」。編集の際は「音楽で説明しないよう心がけている」とも話す。「フィクションは別の方法を取るけれど、今回のようなタイプの作品では、サウンドとテキストとイマージュの一体感を常に意識しています。いわばコラージュ。私はコラージュが大好きなんです。いろんなものを重ねて貼ったり、日曜大工のように組み立てたり。そして、物を書くようにそれらを編集していくんです」
ひとつの質問への回答が15分以上に及ぶことも。様々な事象をつなげて現代社会への危機感を語る様子や時おりのぞくユーモアは、パン監督の映画さながら。映画祭の締めくくりにふさわしい充実した時間となった。
文・深津純子
写真・吉田留美、明田川志保