11月7日(土)、有楽町朝日ホールで特別招待作品『デニス・ホー:ビカミング・ザ・ソング』が上映された。本作は、『奪命金』(11)などで俳優としても知られる香港の歌手デニス・ホーさんの歩みを追ったドキュメンタリー。アーティストとしての彼女の魅力に加え、同性愛者であることを公表し、香港の民主化運動に参加するなど、1人の人間としての生き様が収められている。上映後にはリモートによるQ&Aが行われ、アメリカにいるスー・ウィリアムズ監督が、観客の質問に答える形で製作の舞台裏を語ってくれた。
「長年、中国で映画制作を行い、香港でも長い時間を過ごしてきました」と自己紹介したウィリアムズ監督だが、当初はデニスさんのことを全く知らなかった。共通の友人に紹介され、2人が初めて出会ったのは2017年の夏。「一週間ほど一緒に過ごし、人生や音楽について様々な話を聞くうちに、デニスのアーティストとしての姿勢や生き方に共感し、映画を制作しようという話になりました」。
こうして2018年に撮影を開始。2019年10月の完成を目指していたところ、香港の民主化運動が始まる。そこでの彼女の姿も捉えたいと考え、2019年末まで撮影を継続し、映画が完成したのは2020年3月だった。
ただ、作中でも言及されている通り、デニスさんはかつて香港の民主化運動に参加したことが原因で、現在は中国国内で活動できない。そのため、「周囲の人たちに、彼女について語ってもらうことは非常に難しかった」とウィリアムズ監督は打ち明けた。
「長年、デニスと一緒に仕事をし、彼女を心から尊敬している人でさえ、『話すのが怖い』と。音楽界でも、映像界でも、友人関係でも『カメラの前では話せない』と何度も言われました」。作中では、その困難を乗り越え、デニスさんの友人で歌手のアンソニー・ウォンが証言を行っている。
また本作には、民主化運動で警察とデモ隊が衝突する様子を至近距離で捉えた生々しい映像も収められている。これは、予算的な都合で香港に行けなかったウィリアムズ監督が、現地のチームに撮影を依頼したもので、デニスさん自身も撮影に参加。「冒頭で警察が彼女に迫るシーンは、彼女と彼女のアシスタント数人が、スマホで撮った映像です」。
ところが、当時は自由にできた撮影も「今年の夏に成立した国家安全維持法によって、全てが変わってしまった」といい、香港を取り巻く状況が厳しさを増していることを窺わせた。
一方、アーティストとしてのデニスさんの歩みも追った本作では、彼女のヒット曲が全編を彩る。その選曲作業を「大変でした」と振り返ったウィリアムズ監督は、「彼女には膨大なディスコグラフィーがあるので、『キャリアの中で特に大事な曲は何か』と尋ね、出してもらったリストに基づき、使う曲を決めました」と、そのプロセスを説明。さらに、「アーティストとしてのデニスを、アジア外に紹介したい」という意図から、歌詞の英語翻訳では「広東語の細かい機微は伝わらないかもしれないが、ポップソングとして、映画を見てくれた方に響くように」という点を心掛けたとのこと。
現在も連絡を取り合っているが、「監視されていることはわかっているので、あまり話し過ぎないように気をつけています」というウィリアムズ監督は、デニスさんの近況を次のように語ってくれた。「彼女は香港を出るつもりはないと思います。私には、以前より香港という場所にコミットしているように見えます。今はポッドキャストや音楽制作に励んでおり、『アーティストとして、自分が香港のためにできることはまだある』と考えているのではないでしょうか」。そして「大変勇敢な女性です」と評した。
現在の公開状況について「香港では不可能。コロナ禍のためアメリカではバーチャル公開されたが、全体的にはかなり消極的な印象。フィルメックスのような勇気ある配給会社や団体はまだまだ少ない」とウィリアムズ監督が悔しさを滲ませた本作は、映画祭終了後、期間限定ながらオンライン上映が予定されている。ぜひこの機会に、本作を通じてデニス・ホーさんの勇気ある生き様に触れてほしい。
(文・井上健一)
ニュース/デイリーニュース
【レポート】『ハイファの夜』リモートQ&A
11月6日(金)、有楽町朝日ホールで、特別招待作品『ハイファの夜』が上映された。本作は、アモス・ギタイ監督の故郷イスラエル第三の都市ハイファのナイトクラブに集う人々の人間模様を通して、ユダヤ人とアラブ人の共生の可能性を探った群像劇。今年のヴェネチア国際映画祭コンペティション部門にも出品された注目作だ。上映後にはリモートによるQ&Aが行われ、フランスにいるギタイ監督が、観客の質問に答える形で撮影の舞台裏を語ってくれた。

物語の舞台となるナイトクラブは実在の店。前作『エルサレムの路面電車』(2018年第19回東京フィルメックスで上映)の出演者の案内でダウンタウンを訪れたことが、ギタイ監督がこの店と出会うきっかけになった。「アラブ人とユダヤ人が集まって、いろんな話をしたり、口喧嘩をしたり、様々なことが一か所で起こっている“ごちゃまぜ感”が気に入った」と語るギタイ監督。そこで、「ハイファについての映画を作る上では、この場所が最適ではないか」と思いついたという。
「この映画を作る上で参考にした映画はあるか」との質問には「私は映画学校で学んだわけではないので、古典的な作品を参考にして映画を作る習慣がない」としながらも、「強いて挙げれば」と前置きし、ジョン・ヒューストン監督の遺作『ザ・デッド/「ダブリン市民」より』(87)を挙げた。その理由は「一直線に進むひとつの物語ではなく、様々な人々の人生の断片が、たまたま一つの場所に集まった中から、街の姿が見えてくる。そういう手法で物語を綴る映画として、似ているところはあるかも」とのこと。
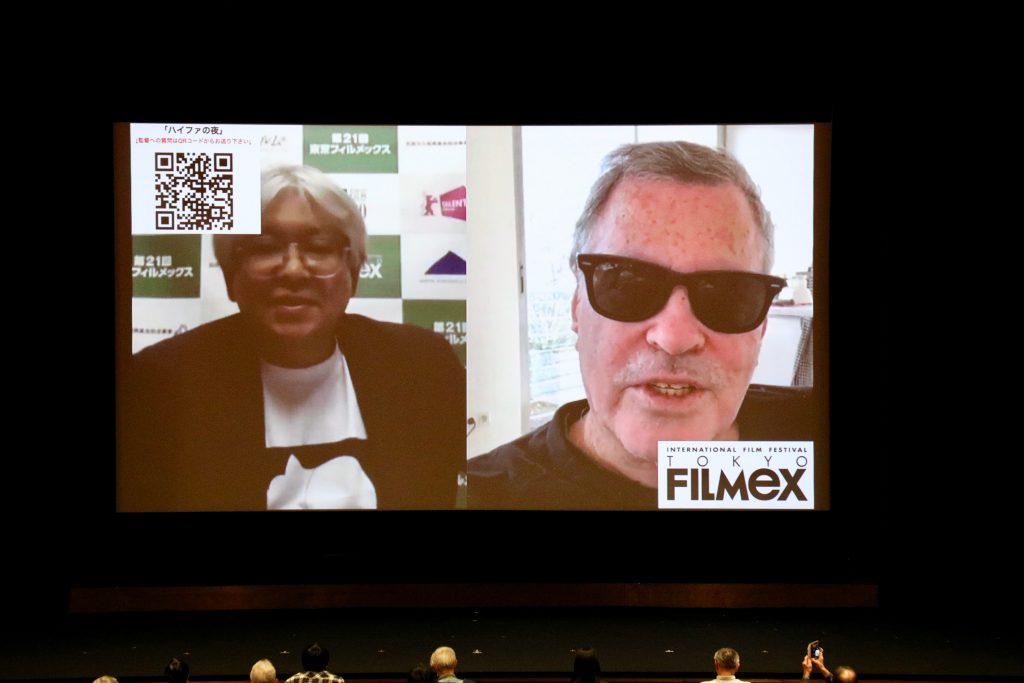
さらに、そのストーリーテリングの手法は、「現代を描く上でも重要」と語り、「現代は、人間の生き方が断片化している。多くの人たちは、一か所に留まることなく、色々な土地を移動しながら人生を歩もうとする。だから、それぞれの場所に自分の人生があり、それが必ずしも一つにつながっていない」と独自の人生観を披露。その上で「現代の映画がすべきなのは、そういう断片化した私たちの人生を、映画でどう表現するかにチャレンジすること」と持論を展開した。
これを踏まえて、本作に込めた思いを次のように打ち明ける。「この映画では、性的マイノリティの人もそうでない人も、あるいはアラブ人とイスラエル人、男性と女性など、様々な立場の人たちが、自分の人生の断片のひとつとして、このクラブに集まっている。そうやってみんなが近くに存在することで、相互理解が生まれるかもしれない。もし生まれなかったとしても、同じ場所で共存することはできるかもしれない。そこから、新しい人間のあり方を提示できるのではないかと考えました」。
一方、舞台となるナイトクラブに集う人々の息遣いをリアルに伝えるのが、陰影を生かした深みのある色彩と、流麗な移動撮影が印象的な映像美だ。本作の撮影を担当したのは、オリヴィエ・アサイヤス、ウォルター・サレスなど数々の名匠と組んできたエリック・ゴーティエ。是枝裕和監督の『真実』(19)にも参加し、ギタイ監督とはこれが四度目のタッグとなる。そのゴーティエをギタイ監督は「非常にフレキシブルな人物」と評し、「この映画のように、彼が外国で撮影するときも、地元のクルーと積極的に交流し、共同作業ができるところが素晴らしい」と絶賛。

2人の共同作業ついては、「まずその場所をどう撮るのか、一緒に“場所を見る”ことから始まる」「俳優との話し合いにも極力、立ち会ってもらう」と創作の秘密の一端を明かしたギタイ監督。「ひとつひとつの作品で、撮影する場所やテーマに合わせて、新しい映画の表現を作り出していこうと野心を持って共同作業をしている」とも語り、互いの相性の良さを伺わせた。
故郷ハイファに対する思いが詰まったギタイ監督入魂の本作。現時点では日本での劇場公開は未定だが、何らかの形で幅広く鑑賞する機会が訪れることを期待したい。
(文・井上健一、写真・明田川志保)
【レポート】『迂闊な犯罪』リモートQ&A
11月2日、コンペティション部門『迂闊な犯罪』がTOHOシネマズ シャンテ スクリーン1で上映され、上映後には、アメリカに滞在しているシャーラム・モクリ監督とリモートでQ&Aが行われた。本作は、イランの映画館レックス劇場の放火事件をモチーフに、現在のイラン社会をシネマ・イン・シネマの形式で描いた作品。リモートスクリーンに登場したモクリ監督は、「劇場まで足を運んでいただきありがとうございます。劇場で映画を観ることが夢のようなことになっていますが、みなさんと一緒に劇場に座って映画を観られるようになることを願っています」と観客に挨拶した。

まず、映画の中に映画が入れ子のように組み込まれている複雑な構成について説明を求められたモクリ監督は、次のように答えた。
「私は基本的にシネマ・イン・シネマの形式を好んでいます。アッバス・キアロスタミ監督の『クローズ・アップ』(’90)や『オリーブの林をぬけて』(’94)でもこの手法が取られていましたし、シネマ・イン・シネマをいつか試したいと思っていました。レックス劇場の事件を題材にしたいと思っていたところ、これこそシネマ・イン・シネマで撮りたいと考えました。」
複雑な構成にも関連するが、本作では時間軸が螺旋のようにずれる。モクリ監督は、「過去の事件のキャラクターたちを現在に置き換えて語ろうとすると、過去と現在を行き来できるように時間軸をずらすことを思いついた」と語った。
続いて、タイトル(英題:Careless Crime)に込められた背景や意図について話が及んだ。レックス劇場の火災事件については、反体制運動を抑圧する目的で反体制派にその責任を押し付けようとする政治的な側面から説明されることが多いそうだが、モクリ監督は、事件当日に一体何が起こったのかということを解き明かすために、自ら裁判資料などを調査したという。その結果、政治的なものではなく、単なる不注意で起こった事件ではないかと考えるようになったとか。劇中でも使用されているサイレント映画『The Crime of Carelessness』(1912年、ハロルド・ショウ監督)には、不注意で工場が燃えてしまうという設定があることから、本作のタイトルはそれに倣ったという。
一方、事件当日のレックス劇場で上映されており、本作でも映画内映画として引用されているマスード・キミヤイー監督の『鹿』(‘74)は、革命後、公開が許可されていないという。革命前に制作された映画作品の多くは、革命後に許可されておらず、その理由としては、革命前の映画に登場する女性がスカーフを被っていないなど、革命後の社会の変化とも関連しているとのこと。

続いて、撮影時のカメラとライティングについての質問に移った。照明を直接カメラに当てて、画面が白くなる場面があるが、どのような効果を狙っているのかと問われると、モクリ監督は、3つの狙いがあったことを明かしてくれた。その3つの狙いとは、映画館の映写機のような光を表すこと、炎を感じさせる光を表すこと、混乱した精神の状態を表すことだったという。また、本作は異なる時間と異なる場所が複雑に絡み合う構成のため、複数のカメラを使用したと思われる本作だが、実際に使用したカメラは1台のみだったとか。フォローショット、フィックスショットなどテクニックを駆使し、いろいろな角度からシーンを撮っているため、複数のカメラで撮影したかのように見えるとモクリ監督は説明した。
最後にモクリ監督は、「素晴らしい質問をありがとうございました」と観客に謝辞を述べてQ&Aを締めくくり、観客から大きな拍手が送られた。
(文・海野由子)
【レポート】『不止不休(原題)』リモートQ&A
11月1日、コンペティション部門『不止不休(原題)』がTOHOシネマズ シャンテ スクリーン1で上映され、上映後には、北京にいるワン・ジン監督とリモートでQ&Aが行われた。本作は実在の新聞記者をモデルに、田舎から上京した青年がB型肝炎キャリアに対する社会的差別に着目し、新聞記者として成長する姿を描いたワン監督の長編デビュー作。
まず、本作で実在の新聞記者ハン・フードンをモデルにした制作経緯について問われると、ワン監督は社会派作品への熱い思いを次のように語った。
「電影学院を卒業して以来、第1作目ではどのようなものを撮るべきかとずっと考えてきました。電影学院で映画美学を学び、理想としては現実主義的な、社会派の映画を撮りたいと思っていました。中国は広大で、人口も多く、社会ではさまざまな事が起こっています。個人的な問題ではなく、社会的な問題に目を向けて、向き合っていきたいと思いました。主人公の新聞記者はペンを持って社会を見ていますが、私はカメラを持って社会を見ているという点でつながりました。」

続いて、バイ・クーさんを主演に起用した理由について訊かれると、シンプルな理由だと応じたワン監督。とういうのも、脚本を書くときからバイ・クーさんが頭の中にあり、ごく平凡な人の雰囲気が欲しかったという。中国では、バイ・クーさんはネットの短編作品で有名だそう。そうした作品では、毎回、厄介なことに出くわしながらも生きていくという大衆的なイメージがあり、本作の主人公ハン・ドンのイメージにぴったりだったという。
次に、2000年代に北京に留学していたという観客から、当時と現在では北京の街が様変わりしているため、撮影に苦労したのではないかと問われた。屋内の撮影については、スタジオを使用していたため、取材を行って、2003年当時の雰囲気を再現することはコントロール可能だったというワン監督。ただし、問題だったのはやはり屋外の撮影で、北京の風景の変化があまりに激しいため、いっそのこと別の場所に変えようかとも考えたとか。しかし、「これは北京でしか撮れない。なぜ多くの人が北京に惹きつけられるのかというのを出さなければならない」と思い直したそうだ。
さらに、リアリズムに徹していながら、劇中、ペンと新聞が浮遊するシーンにはどのような意図があるのかと訊かれると、「ふと思いついた演出で、急にアイデアが浮かんだ」と答えたワン監督。中国で2003年を象徴する社会的な出来事として、SARSと有人宇宙飛行の成功の2つが挙げられるそうだが、監督自身、宇宙好きという。「宇宙への夢は人類な壮大な夢で、ハン・ドンの夢は小さな夢だが美しく、夢はどれも同じ。そう考えると、ペンも空中に飛んでもいいのではないかと思いました。こういうシーンの解釈は、見た人の解釈に委ねたいので、自分の解釈を言いたくなかったのですが…」と、ワン監督は少しためらいながらも丁寧に説明してくれた。
最後に、このウィズ・コロナ(with Corona)の時期に本作を観ると感慨深いものがあるという観客からは、制作時期はパンデミック前だったのかという質問が挙がった。ワン監督によると、撮影自体は昨年11月から春節(旧正月)頃まで行われ、その時点ではまだパンデミックが明確ではなかったが、ポストプロダクションは完全にパンデミック時期と重なり、すべてリモートで行ったという。「コロナ禍で映画制作を続けるにあたり良かったことは、十分な時間があったということです。試行錯誤しながら、思索により多くの時間をあてることができました。そして、編集スタッフと意見が合わないときは、画面をオフにすればいいだけのことだと言い聞かせました。直接顔を合わせると喧嘩になってしまいますから(笑)」と、ユーモアを交えて語ってくれたワン監督。

ここで時間切れとなりQ&Aは終了した。ほぼ満席の会場では、観客から多くの質問が寄せられ、本作への関心の高さがうかがえた。本作は、詳細な時期は未定ながら、来年日本で公開される予定である。
(文・海野由子)
【レポート】『水俣曼荼羅』 Q&A
10月31日(土)、TOHOシネマズシャンテにて特別招待作品として原一男監督『水俣曼荼羅』が上映された。本作は日本四大公害病として知られる水俣病の補償を巡って国・県との裁判を戦い続ける患者たちのドキュメンタリーだ。上映終了後、胎児性水俣病患者の坂本しのぶさんのビデオメッセージが上映された。

その後、水俣病の被害者であり「水俣病被害者互助会」の団長である佐藤英樹さん、その妻の佐藤スエミさん、事務局長の谷洋一さんが水俣よりリモート出演した。
まず、市山尚三東京フィルメックスディレクターが映画の感想を尋ねた。英樹さんは「水俣のことよく撮っていた」と語った。スエミさんは「被害者が辛い思いをしている水俣病は今も解決に至らないのは、国・県の心の醜さであるとわかった」と語った。
続けて、裁判の最近の状況を問われると、国家賠償訴訟は2020年3月に福岡高裁で8人全員が認められず、上告中であること、また、義務付け訴訟はコロナウイルスの影響に遅れていたが、熊本地裁で2020年11月より再開されるとコメント。
市山ディレクターは「本作は今後全国公開されると、水俣病問題に対する日本の人々の認識が高まると思う。今後の裁判がいい方向になるように祈っている」とコメントし、それに対して、英樹さんは「水俣病は全国的に終わったように報道されているが、まだまだ解決されていないので、まだ解決されていないことや国や県が行っていることを知ってもらいたい」と語った。

最後にスエミさんより、「被害者は皆患者であるのに、国・県は認定する人としない人と平気で差別してきた」という現状の訴えから、被害者のことをわかろうとしない行政への憤り。そして、福岡高裁の判決を受けて、「悪いことをした人が勝ち、何も悪くない被害者が負ける。どう考えても間違っていることが日本で起こっているんです。国・県が心を入れない限り水俣病はいつまでも終わらないと思います」と語った。
その後、原一男監督、二宮正医師が登壇。まず、二宮さんより「水俣病は学生の時から、30年かそれ以上関わってきました。原さんと出会って、映画をなんとか世に出せたこと嬉しく思う」と語り、「坂本しのぶさんを見てわかると思いますが、原因はチッソがメチル水銀を流したことはわかっていますが、結果はまだ(症状が)進んでいるんです。その中でも生きていることが国・県に対しプロテストだと感じています。死ぬまで生きるしかないから、頑張って生きていかないといけないと思います。また、患者以外の支援者の人も水俣病がなかったら全く普通の生活をしたかっただけなのに、どういうわけか皆さんと違う生活をしなければいけなかった」と声を震わせ語ってくれた。
続けて、原監督より「6時間って長さはかかるんだな、と認めていただけると嬉しいです」と笑顔で語った。

市山ディレクターより「裁判の話を追っているストーリーだと思っていたが、途中で二宮さんの医学的な話が語られるシーンがあった。我々が知識的に知らなかったことが明らかにされていて、今に至る問題を提示しているのは予想しなかった」と話した上で、二宮さん出演の経緯を聞いた。
原監督は「二宮さんとは撮影最初からの出会い」だと語った上で、「二宮さんは撮影の途中から裏方さんとして、マイクを持ってもらったりしました。ずっと一緒だったんです」と交友を披露した。
二宮さんは「一番最初から最後まで、編集も一緒」と答えると原監督は「16、7年になるんじゃないか」と回顧していた。
会場からの質疑応答に移った。まず、タイトルの「曼荼羅」に込められた意味についての質問が挙がった。原監督は「私がやるまでは土本典昭監督が作医学としての水俣病をテーマにした三部作を作っていらっしゃった。しかし、私は医学にまとめる発想はやめようと思った」と語り、「水俣病は患者だけじゃなく、医学者もジャーナリストも映像の作り手も全部ひっくるめて一つの水俣病世界がある気持ちを込めて作ったので、曼荼羅というタイトルがぴったりすると思っています」と答えた。
続いて、作品をここで完成にしようと思った判断についての質問に対し、気になっている人やエピソードを15年通って「ここまでかな、と自然に思えたところで終わりにしよう」と原監督。
撮影のきっかけについて、大阪電気通信大学の事務局長が関西訴訟の支援をしている人が誘ってくれたそうだ。「100万円出すという話だったが、1,000万円以上出してもらうことになりました」と話すと会場から笑いが漏れた。
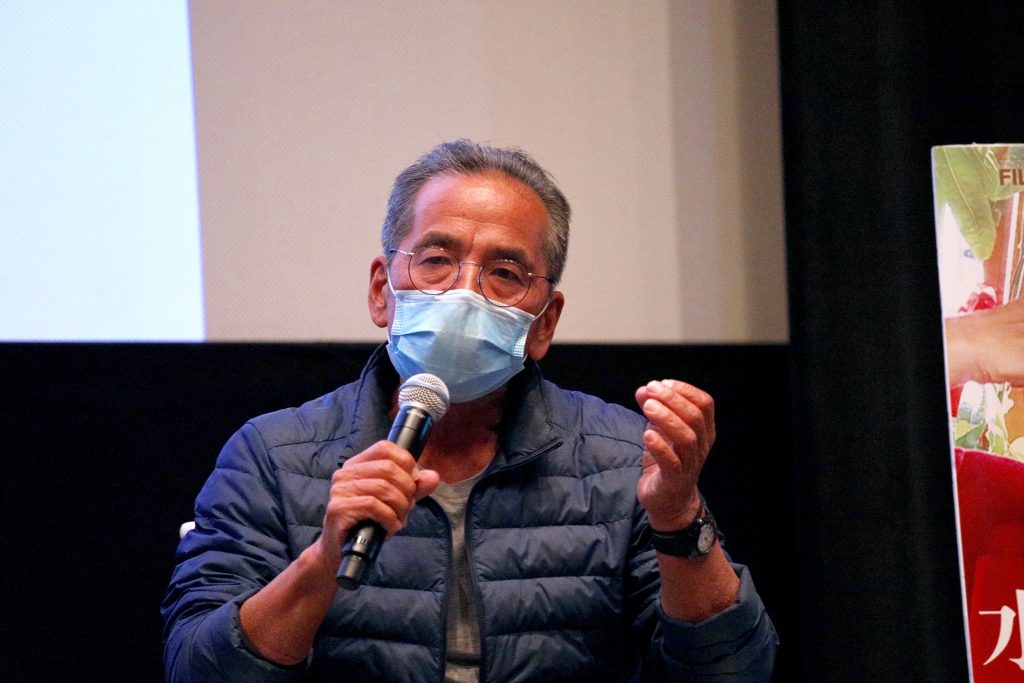
作品に取り組まれて、人が人たる所以をどのように捉えられたか、という問いに対して、まずは二宮さん。「水俣病は人が壊されていった歴史だと思います。人が人じゃなくなっている方向に動いている気がします。峠三吉の原爆の詩の中で“にんげんをかえせ”ってありましたが、私もそういう気持ちがあります」。原監督は「二宮さんの人が人でなくなる、という言葉は簡単に言ってしまうと誤解を与えやすいので、丁寧に説明しないといけない」と観客に語りかけ「人が人でなくなるというのは本作のとても大きなメッセージです。映画の中では五感がやられると表現していますが、それだけじゃ足りません。つまり、人が言っていること、考えていることを理解し、受け止め、整理をする。そして、自分の考えを相手に伝えるというコミュニケーション」と説明し、二宮さんは何かを判断をする脳の中枢に障がいが起こっていると補足した。
原監督は「人間が文明を作ってきた。文明を享受するのは五感」と前置いた上で「今、南極で泳いでいる魚の体内にメチル水銀が発見されているというデータがあります。メチル水銀を含む魚が泳ぎ回っているということは水俣病が地球上至るところで広がっていく可能性を持っているということ。そして文明を享受できなくなるということは人間が人間としての優位性を破壊されることを意味します。従って、日本の中で受け止めるのではなく、全地球規模の問題なんです」と訴えた。

観客からの作品の尺を削る際に気にした点はあるか、という問いについて「シリアスなテーマで扱おうが、エンターテイメントとして作らないと誰も見てくれない」ことを念頭に、「メッセージをきちんと入れつつも、6時間飽きずに面白かったよと言ってもらえるかどうかという感覚があります」と原監督。
最後に市山ディレクターがお二人にコメントを求められ、二宮さんは「自分のやったことは論文で残しました。さらに映像として残っていくのは、後の人がすぐに見られるのでありがたいことだと思います」とコメント。原監督は「正直に言いますと、いい映画だとしても興行が始まったらお客さんが来ないのかもしれないという不安があります。めげずに戦いますが、(観客のみなさんがたくさんの人に)見てと言って、背中を押していただけたらありがたいです」とコメント。
原監督のユーモラスな回答に笑いが起きつつも、水俣病の現状について改めて考えさせられる質疑であった。本作は2021年公開が決定している。
(文・谷口秀平、撮影・明田川志保)
【レポート】「愛のまなざしを」 Q&A
10月30日(金)、有楽町朝日ホールにて、第21回東京フィルメックスのオープニング作品として、万田邦敏監督の『愛のまなざしを』が上映された。6年前に妻を亡くした喪失感に苦しむ精神科医・貴志と、彼に心を寄せる謎めいた患者・綾子の愛憎をスリリングに描いた作品。貴志役を『UNLOVED』『接吻』でも主要人物を演じた仲村トオルさん、綾子役は本作のプロデューサーも兼ねる杉野希妃さんが演じ、『UNLOVED』(2002年)、『接吻』(2008年)に続いて万田監督と妻の万田珠実さんが共同脚本を手掛けた。

舞台挨拶には万田監督、仲村さん、杉野さんと、妻役の中村ゆりさん、共演の片桐はいりさんが出席した。万田監督は「出演者のみなさんがとてもいい、すごくいいです」と開口一番キャストを称賛。「今日来て下さった方々、それから斎藤工さん。脇で出て下さった方たちも、それぞれみんなとてもいい。『この人いいなぁ』『この人誰だろう。ちょっとこれから気にしておこう』ということになっているので、そのあたりもぜひ見ていただきたい」と呼びかけた。

万田監督とは4度目のタッグとなる仲村さんも、「期待以上の作品に仕上っていると思います」と断言。杉野さんは「もともと万田監督のファンで、特に脚本家の珠実さんとご一緒の作品が好き。万田節を思いっ切り出していただきたいと思い、こういう形になりました。実際にご一緒して、今までにないことを求められ、すごく新鮮でエキサイティングでした」。中村さんも「監督の世界観が明快なので、こちらはただ身を委ねるだけ。万田ワールドを体験できて楽しかったです」と振り返った。
観客として東京フィルメックスに毎年通っているという片桐さんは、「今回ここに立っていることにちょっとびっくりしています」とあいさつ。「トオルさんから監督のことを『すごく怖い』『すごく細かい』と聞いていたので、どんな目に遭うんだろう、と。最初の演技で『あ、ちょっと違うかも……』と思ったら、『ちょっと違いますね』とすぐおっしゃったので、この監督の言葉には従って行こうと思いました」と告白。「作品はこれから客席で拝見しますが、ここに呼ばれたということは(出演場面が)カットされていないと思うので、安心しています」と語り会場の笑いを誘った。

上映後のQ&Aには万田監督、仲村さん、杉野さんの3人が登壇した。新型コロナウイルスの感染対策で、質問は客席からの口頭ではなく、スクリーンに投影したQRコードのサイトに書き込んでもらう方式を採用した。
質問を寄せてもらう間、市山ディレクターが製作の経緯などについて尋ねた。万田監督によると、杉野さんから「精神科医と患者が恋に落ちる」という基本設定を提案されたのが出発点。「杉野さんのアイデアに妻の珠実が手を加えて話を作っていきました。斎藤工さんが演じた義弟の存在なども珠実が考えてくれたと記憶しています」という。
脚本を読んで、仲村さんは「難しいな」と感じたという。「ただ、万田監督の作品なので、自分が難しさを克服する必要はないだろうとも思った。ちゃんと撮って下さるという絶大な信頼感があったので、撮影のスケジュール以外、ほとんど不安はありませんでした」
その撮影日程はについては、「かなり濃密というか、ものすごい勢いの撮影だった」と仲村さん。万田監督も相当きついなと思って怖かったのですが、やってみたらスイスイさくさく終わった」という。
スムーズな進行で、その日の予定になかった仲村さんの超重要シーンの撮影が突如追加されたことも。「時間が余ったのでトオルさんにやってもらおうと言ったら、『えっ、そのシーンやるの?』って……(苦笑)。もちろんやって下さったんですが、『この重要な芝居をいきなりやらせるのか、お前は』と内心めちゃくちゃ怒っていたのかもしれません。でも、あのシーンはすっごくよかった」と万田監督。「きちんと謝っていなかったので、すみませんでした」と頭を下げる監督に仲村さんも苦笑い。「本読みやリハーサルをクランクイン前にやっていたので、できたのだと思います。監督の撮影は速いけれど、せっかちではない。決断が速いとか、そういう速さです」と付け加えた。

会場からは、仲村さんが見せるジグザグ歩きがルイス・ブニュエル監督の『エル』の引用ではないかとの質問が。万田監督の答えはYES。「仲村さんはあそこでジグザグに歩くことを自分の芝居としてどう処理するか、かなり悩まれたみたいですね」と万田監督。「結果的にわからないままやりました」という仲村さんを「わからなさ加減がよかった。狂気に入っていく感じがよく出ていました」とねぎらった。
診察室に飾られた印象的なトンネルの絵についても質問があった。万田監督の亡くなった知人の作品で、脚本完成後に診察室に絵を置こうと考えて選んだのだという。「脚本上はラストは別の設定でしたが、絵とリンクさせようと考えて変えました。実際のところ、あの絵がなかったらこの映画は中心点を見つけられなかったのではないか。とても助けられました」。
「体の動きを決めたら、心もついてくる」という万田監督の演出術について、主演の2人に尋ねる質問もあった。仲村さんは「僕の受け取り方ですが、心がついていかなくても、それが観客に伝わる感じがします。ほとんどのシーンでそういうものがある。たとえ理解しないままでも、心がついていかなかったとしても、伝わるものは小さくない。それが万田監督の演出にいくつもある素晴らしさの一つだと思います」と信頼を寄せた。杉野さんも「監督から演出された動きがあまりに想像を超えていると、段取りの時に笑ってしまったり。でも、実際に本番でやると、気持ちがついてくるというより、自分が想像していなかった新鮮な感情が湧くことが多かったです」と万田マジックの魅力を語った。

仲村さんはこの日の舞台挨拶の準備で、『Unloved』のメイキング映像を前夜に見返したという。「当時の監督は本当に怖かった。『答えはこれしかないです』という風だったのですが、今回は『答えはこれしかないと思うんですよ、へへっ』と笑いながら演出して下さった気がします」というコメントは、長年培った信頼の深さをうかがわせた。「『Unloved』のメイキングで、当時の自分のインタビューの態度がものすごく感じ悪かったんです(笑)。あの作品の撮影中は、どういう人物になるのかまったく予想できず、その不安からすごく虚勢を張っていたのだと分析しています。『接吻』の時は脚本を読んですごい映画になると思い、試写を見たら予想通りの方向で予想以上にすごい映画になっていた。今回も、予想通りの方向で予想以上にすごい映画になっています」
「愛のまなざしを」は映画は来年春に劇場公開予定。
(文・深津純子、写真・明田川志保)
【レポート】第21回東京フィルメックス 開会式
第21回東京フィルメックスの開会式が10月30日(金)、有楽町朝日ホールで開かれた。今回から東京国際映画祭と連携して会期がほぼ同時期に設定され、例年より約2週間前倒しでの開催となった。新型コロナウイルスの流行で世界の映画祭が大きな影響を受けるなか、東京フィルメックスは例年通り9日間の日程で、コンペティション・特別招待作品・特集上映・映画の時間プラスの4部門で30作品をリアル上映する。

開会式の会場となった朝日ホールは、コロナ対策で入場者を50%に制限。客席には1席ごとに「一定の間隔を空けてお座り下さい」のメッセージを掲げ、ソーシャル・ディスタンスへの協力を呼びかけた。例年とは様変わりした光景だが、客席からはいつもと変わらぬ静かな高揚感が伝わってきた。
開会式では、まず市山尚三ディレクターが登壇し、「コロナ禍で開催がどうなるかを考えつつ準備をしていったのですが、なんとか初日を迎えることができました。スポンサーの方々、ご協力いただいた団体の方々に感謝申し上げます」とあいさつ。「今年は残念ながら海外のゲストをお呼びすることができず、リモートでQ&Aをやるなど、かなりイレギュラーな形になります。試行錯誤で皆様にご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、どうか大目に見ていただき、ぜひとも1本でも多くの作品をご鑑賞いただければと思っています」と語った。

続いてコンペティション部門の審査員が紹介された。委員長はオープニング作品「愛のまなざしを」の万田邦敏監督。ほかに、映画評論家のクリス・フジワラ(米国)、トム・メス (オランダ)、 アンスティチュ・フランセ日本の映画プログラム主任の坂本安美、アミール・ナデリ監督の「CUT」「Monte(山)」などを手掛けたプロデューサーのエリック・ニアリ(米国)という国際的に活躍する各氏が審査員を務める。
審査員を代表してあいさつした万田監督は、「この大変な時期にお越し下さってありがとうございます」と切り出し、「コンペティションには12本のアジアの新しい作品がそろいました。審査員はまだ誰も作品を見ておりません。お客様と一緒に会期中に1本ずつ見ていくことになります。どのような作品にめぐりあえるのか、とても楽しみにしています」と上映への期待を込めた。

会期中の11月2〜7日にはアジアの若手映画監督や製作者を育成する「タレンツ・トーキョー2020」もオンラインで開催する。会場で見られなかった人のために、コンペティションなどの一部作品は閉幕後にオンライン配信も予定する。また、特別上映として、マノエル・ド・オリヴェイラ監督の6時間50分の大作「繻子の靴」も11月22日に朝日ホール、11月26〜28日にアテネ・フランセ文化センターで上映。いつも以上にじっくりたっぷり楽しめるプログラムとなっている。
(文・深津純子、撮影・明田川志保)
【レポート】『由宇子の天秤』 Q&A
11月1日(日)TOHOシネマズシャンテ1にて東京フィルメックス・コンペティションの『由宇子の天秤』が上映された。本作は春本雄二郎監督長編映画第2作であり、脚本が2019年のフィルメックス新人監督賞ファイナリストに選出されている。

上映終了後のQ&Aには、春本雄二郎監督、プロデューサーの片渕須直さん、松島哲也さんが登壇した。まず、春本監督は「本作が日本初上映できたことを嬉しく思います。また本作に関わったすべての人に感謝します」と語った。続いて、『この世界の片隅に』(16)の監督であり、本作ではプロデューサーを務める片渕さんは「本作を世の中に出すにはどうしたらよいだろうか、というところから関わらせていただいて、それが日本で皆さんの前に公開することができた」と感慨深げに話した。また、松島プロデューサーも「日本で上映することができて嬉しく思っている」と語った。
まず、市山尚三東京フィルメックスディレクターより、片渕プロデューサーに作品に関わった経緯を尋ねた。元々は片渕プロデューサーと松島プロデューサーが同じ映画監督として「自分のモノ作りがどうやってできるんだろう」とお互い相談し、応援しあう間柄だったそうだ。その後、松島プロデューサーに春本監督を紹介される形で制作に関わったと語った。「プロデューサーといっても、ボクシングでいうとセコンドの後ろにいるカットマンだと思っていましたが、春本監督が被弾しないので出る幕がありませんでした」と言うと会場から笑いが。

松島プロデューサーは18年前に春本監督と出会ったそうだ。その後、「春本監督が『かぞくへ』(16)を見てほしいと連絡してきたのが再会の始まりでした」と語る。その後、本作の脚本を見てほしいと春本監督に言われて、できることがあればと思い参加したとのことだった。
春本監督に着想の発端について尋ねたところ、「2014年の4月頃、助監督を続けていまして、その年に自分は映画を撮るつもりでいました。その題材を探していた時に、小学校のいじめ自殺事件を見つけたんです。そのニュースは被害者の子供ことではなく、加害者の子供の父親と同姓同名の人が被害に遭ったというニュースだったんです。なぜ社会的に全く関係のない人たちからネットリンチを受ける時代になってしまったのか」と理由を語った。
市山ディレクターが「お金を集めるという点で、決して簡単な題材ではないと思いますが」と問うと、春本監督は「扱う題材が題材だけに日本の通常の商業映画の枠組みで作ることは難しいと思った」と語った。「『かぞくへ』を撮った際、スタッフ・キャストはノーギャラだったんですけど、2作目はそうしたくもないと思いました。そこで『かぞくへ』を公開しながらクラウドファンディングを募り、松島さん、片渕さんも融資してくれました」と資金集めの難しさを語った。
また、松島プロデューサーは「監督がやりたいことを自己プロデュースしながら制作していく。もちろんお金はかけられない、題材は地味な部分ではあるんですけど、中国や韓国の人々の心に届いた。次は春本監督も3作目になりますが、若い人たちも自分でプロデュースをするということやってみたらいいと思っています」と語った。
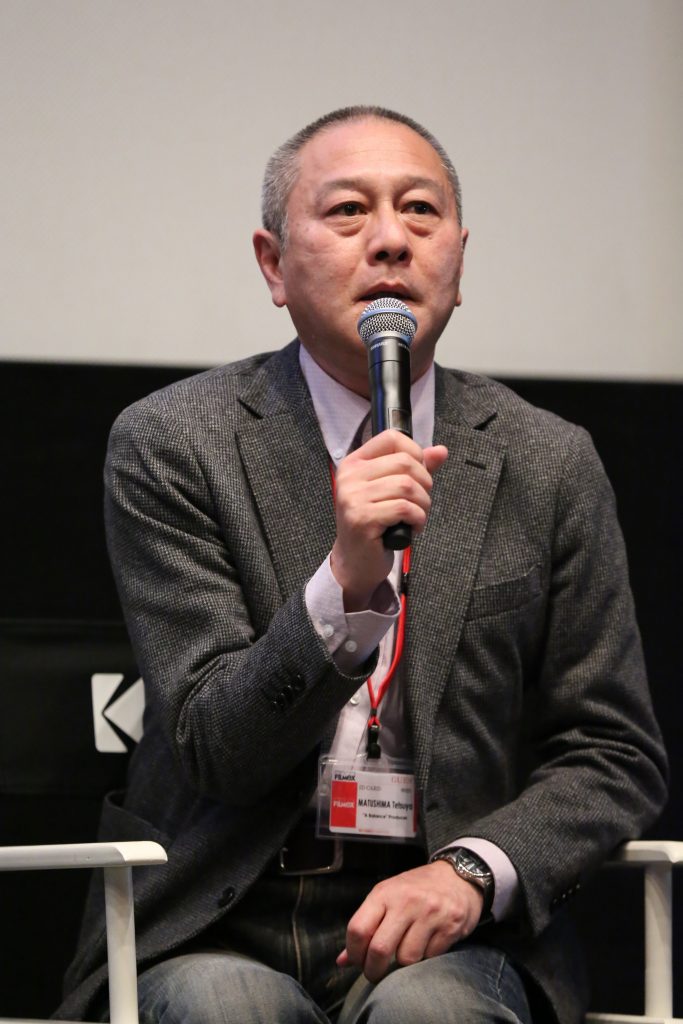
市山ディレクターより本作が中国の平遥国際映画祭で審査員賞と観客賞のダブル受賞をしたこと、韓国の第25回釜山国際映画祭ニューカレンツ部門では最高賞に当たるニューカレンツアワードを受賞したことを報告すると、会場から大きな拍手が。
続いて観客からラストシーンは最初から決まっていたのか、という質問が挙がった。ラストシーンは途中まではもう少し救いのある脚本だったが、しっくりこなかったそうだ。「本当に問うべきところはどこか、を悩みました」と春本監督。松島さんや片渕さんのアドバイスを受けてラストシーンが出来上がったとのこと。
主人公の女性の描き方へのこだわりはあったのかと訊かれると、春本監督は「意図したわけではなく、シナリオを描き終わったときに気づき、映像になってさらに自覚した」と前置きし、由宇子が女性であるというのは、父親と娘という関係性だからこそ、ストーリーに衝撃を与えると語った。また、「ドキュメンタリー作家として戦うフィールドで、男性と女性だった場合、どちらが鮮明に見えるだろうか」ということも考え、主人公を女性としてシナリオを作り始めたそうだ。また、加害者家族も意図せず女性だったが「結果として、生き残って耐え忍んでいたのは女性だったと書き終わって気づきました」と春本監督。「日本社会において、未だに戦わなくてはいけない側は女性なのかもしれない」と語った。
タイトル『由宇子の天秤』に込められた意味について問われると、松島プロデューサーが「信じるものが揺らいでバランスを壊して倒れた時、どう立ち上がるのか。秘密と嘘を現代人は抱えていながら、人と関係を結んでいく。その中で天秤のように揺れ動くというのが象徴的に思いました」と解釈した。片渕プロデューサーも「嘘が絶対的なものではなく、相対的なもので、何かのバランスがずれただけで、真実や事実や嘘は全部同じではないか。それらが天秤の中でゆらゆらしているのがまさにこの題名だ」と語った。
質疑応答はここで終了。

片渕プロデューサーより「自分が映画を制作するとき、歴史的事象を調べるが、今残されている人たちの言葉から知るしかないわけです。しかし、残らなかった人の言葉、消されてしまった言葉もあります。たまたま、あるいは意図的に残された言葉が歴史の1ページを形作っているなら、その周りの言葉をもっと知らないといけないと思います。春本監督の脚本にはそれが語られていて、自分が本作に入れ込む原動力になりました。この作品が何か世の中の1ページとして残る言葉となってほしい」と振り返る。
松島プロデューサーは「みんなが理解できるエンディングを敢えて作らないことが騒めきとなって、観客がそれを持ち帰って自分の中で答えを探す。これが本作の魅力だと思います」とコメント。
最後に春本監督より「制作中、正しさとはいったい何なのかと考えました。誰かから見た正しさは、他の誰かから見て正しさではないのかもしれない。絶対的な正しさは存在しない、ということをこの映画で感じてもらいたい。私自身の角度からこの映画を作っただけなので、それを受け取っていただいて、皆さん自身の中で新たな解釈を作っていただけたら、と思います。私はそういう映画を作っていきたいと思います」と観客に語りかけた。
本作は現在公開準備中で、来年公開を目指している。
(文・谷口秀平、撮影・白畑留美)
映画の時間プラス『なぜ君は総理大臣になれないのか』大島新監督Q&A
10月31日、TOHOシネマズ シャンテ スクリーン1にて、『なぜ君は総理大臣になれないのか』の日本語字幕・音声ガイド対応のバリアフリー上映会が行われた。本作は、大島新監督が、衆議院議員・小川淳也さんを17年間にわたって撮影し続けたドキュメンタリー作品。今年6月に都内2館で公開されて以来、その評判が口コミで広がり、上映館数は現在までに全国70館を超え、大きな話題を呼んでいる。
本作の上映後には、音声ガイドを制作した松田高加子さん(Palabra株式会社)の司会進行により、大島新監督のQ&Aが行われた。観客から拍手で迎えられた大島監督は、「まだ新型ウイルス感染の不安がある中で、ご来場いただきありがとうございます。東京フィルメックスという映画祭で上映していただき、なおかつ、ミニシアター系劇場が中心のドキュメンタリーではなかなか上映が難しいTOHOシネマズさんで上映していただき、とても嬉しいです」と挨拶した。
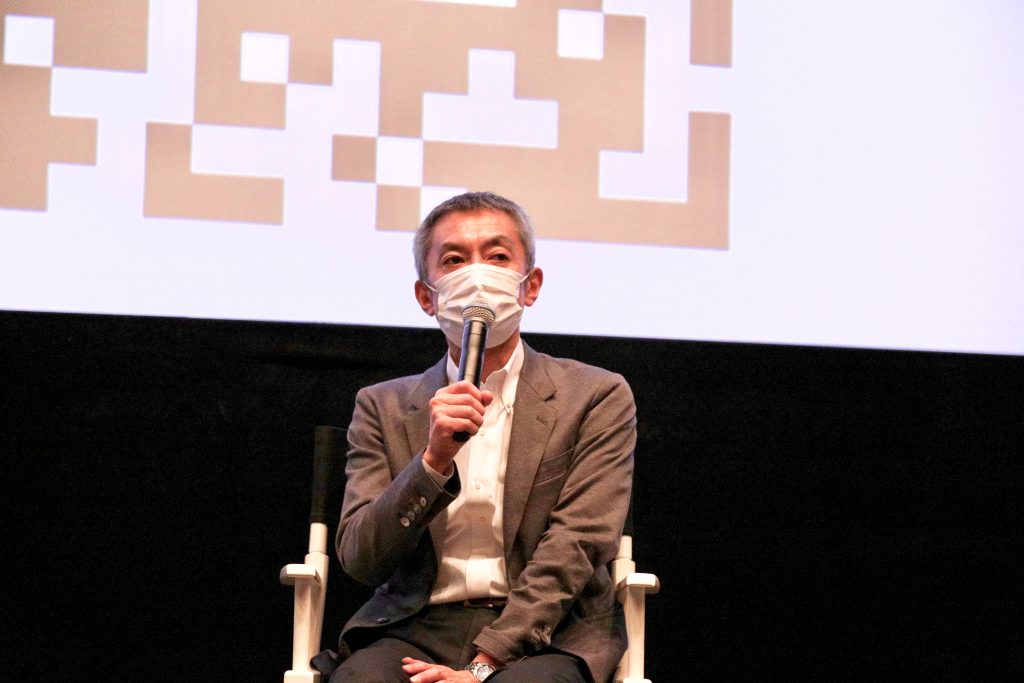
東京フィルメックスでは、新型ウイルス感染予防に配慮して、観客がQRコードを読み取って質問する形式がとられているが、観客からの質問を待つ間、松田さんは、音声ガイドの原稿を書いている間、大島監督と一心同体になるような瞬間があったことを明かしてくれた。そして、大島監督が小川議員をじっと観察しているかと思えば、突然、「総理大臣になりたいですか」と議員に切り込むタイミングが実に刺激的だったと語ると、大島監督は次のように応じた。
「ドキュメンタリーは、被写体との距離感が重要です。その場で起きていることをきちんと記録することが1つ目にあって、さらに取材者としてどのように介入していくかということには最も頭を悩ませているところで、そこが作り手の持ち味になると思います。私は、人物ドキュメンタリーを撮るときに、右手に花束、左手にナイフと思っています。信頼関係がないとそもそも撮影ができませんが、ただ相手のことが好きですというだけでは見ごたえのあるものは作れません。場合によっては、被写体が撮られたくないもの、見せたくないものも、意味があるものは引き出していかなければならないと思います。」

また、松田さんは、映像を音声で届ける音声ガイドならではの難しさを垣間見せてくれるエピソードも紹介してくれた。それは、2017年衆議院議員総選挙活動中に苦戦を強いられていた小川議員が、駐車場に停めた選挙カーの中で後部座席にいた大島監督に語りかける場面でのこと。助手席にいた小川議員の横顔がとても印象的だったため、その様子をあえて音声ガイドの原稿に取り込んだという。後日、その部分に対して大島監督から確認が入ったものの、最終原稿には残されたそうだが、「あれは主観的なものが入ってしまった」と振り返った松田さん。それに対して大島監督は、「あのシーンはとても重要で、長い付き合いがあったからこそ撮れた場面です。我々は、ドキュメンタリーの神が下りてきた、というような言い方をするのですが、こちらから問いかけたわけでもなく、カメラが回っていなかったら成立しておらず、ポロっと出てきたものです。あのシーンは間(ま)が大切で、空気感をそのまま見せた方が彼の苦悩がよく伝わるのかなと思ったのですが。音声ガイドには必要であるけれど、どこまでやるべきか少し考えました」と、迷いがあったことを明かしてくれた。

続いて、会場からの質問に移った。
作品のタイトルを思いついた時期について訊かれると、大島監督は、2016年にこの作品の企画書を小川議員に提出するときだったと答えた。「最初に会った時に、総理大臣になると言っていたのに、社会を良くすると言っていたのに、全然なれそうにないじゃないか」と本人にぶつけようと思って、浮かんだタイトルなのだとか。
また、長年撮影を続けてきて、この時期に本作が公開された理由については、まったくの偶然だったという。作品としてどのように終わらせようかと悩んでいた大島監督は、2017年の選挙が終わった時に編集を始めたそうだが、そこで終わらせてしまうとあまりに救いがないと感じ、少し寝かせて、公開時期を見計らっていたところ、2019年2月に小川議員が国会の質疑で勤労統計調査の不正を追及し、「統計王子」として評判になったことから、完成させる方向に進むことができたという。
さらに続編について話が及んだ。大島監督によると、すでに続編の撮影は始まっているという。「小川さんのような政治家の在り方を問い続けることに意味があるのではないか」と考え、続編でも小川議員の政治活動のポイントごとに取材を続け、政策立案にも焦点を当てたいとのこと。「公開できるかどうかわかりませんが、タイトルが『まさか君が総理大臣になるとは』というような映画になるといいなと思っています。そうならなくても、ひとりの政治家の記録として何らかの形で残したいです」と意気込みを語ってくれた。
最後に、「みなさんの口コミの力がとても大きい作品なので、気に入っていただけたら、ご友人やご家族の方にも推薦していただけたら嬉しいです」と大島監督の言葉で締めくくられ、和やかな雰囲気の中、Q&Aが終了した。本作品はポレポレ東中野をはじめ、全国各地で公開中。音声ガイド版(制作:松田さん、ナレーション:大島監督)にも注目していただきたい。
(文・海野由子/写真・明田川志保)
【レポート】12/1『カミング・ホーム・アゲイン』Q&A
12月1日、最終日を迎えた第20回東京フィルメックスでは、TOHOシネマズ日比谷12で最終上映が行われた。上映作は、クロージング作品として前日にも上映された特別招待作品『カミング・ホーム・アゲイン』。本作は、1995年に雑誌「ニューヨーカー」に寄稿された作家チャンネ・リーの自伝的な物語に基づき、在米韓国人の家族を描いた作品。上映後には、ウェイン・ワン監督が登壇した。

さっそく質疑応答に移り、まず、本作における料理の意味について問われると、「食べることが大好き」と答えたワン監督。「息子(男性)が母親の料理を再現し、それが母との最後の晩餐になるわけですから、料理は本作を動かす重要な要素」と説明した。さらに、サンフランシスコにある韓国料理の3つ星レストランのシェフをコンサルタントとして起用し、豪華な料理ではなく家庭料理のアドバイスをもらったというエピソードが紹介され、料理へのこだわりをのぞかせた。

続いて、狭い室内をシネマスコープで撮影した意図について質問が及んだ。通常、シネマスコープは動きの多いアクション映画で使われることが多いが、本作では、「狭い室内で展開するミニマルな家族の物語を、あえて広い視野で見せよう」と考えたというワン監督。ただし、狭い室内での撮影には苦労したそうで、部屋の中のシーンのほとんどは、部屋の外から撮影されたとか。そして、自身の映画学校時代を振り返り、そこでシャンタル・アケルマン監督の『ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地、ジャンヌ・ディエルマン』(’75)の固定カメラによる構図の取り方に感動し、何もない空間に意味を持たせることを学んだことを回想した。

次に、画質としては全体的に青色のトーンが印象的だと指摘されると、少し冷たい感じが母親や家族の苦難を表していると説明。それに対してフラッシュバックのシーンでは、少し温かみのあるトーンにしたという。また、室内では自然光を使って撮影したことも明かしてくれた。自然光を上手く使う撮影監督としてネストール・アルメンドロスの名をあげ、晩年、彼が視覚を失いかけたとき、肌で光を感じたという逸話を紹介した。

また、長らく映画を撮るうちに創作に対するスタンスにどのような変化が生じたかという質問に対して、ワン監督は自身の作品を振り返りながら説明。ワン監督が映画を撮り始めた頃、アジアンアメリカンをテーマにした作品はアメリカ的な視点で描かれたものしかなく、監督自身はアジア文化を正しく反映することを意識したそうだ。初期の作品『Dim Sum: A Little Bit of Heart』(’85)、『Chan Is Missing』(’82)、『夜明けのスローボート』(’89)がその例となる。続く『ジョイ・ラック・クラブ』(’93)はハリウッド手法で大成功を収めたが、そこで一つのイメージの枠にはまることに違和感を持ち、『スモーク』(’95)、『ブルー・イン・ザ・フェイス』(’95)で実験的な作品に挑戦したという。それらを経て、『千年の祈り』(’07)以降には再びアジアンアメリカンをテーマに、自分自身を含めた本当のアジアンアメリカンの姿、アジア文化を描くことを意識していると語った。

最後に、ワン監督は、遅い時間にもかかわらず最後まで残ってくれた観客に「皆さんはこの映画祭の最後の生き残り(サバイバー)です」と賛辞を送り、第20回東京フィルメックスの作品上映及びイベントがすべて終了した。
(文・海野由子/写真・明田川志保)

