11月25日(月)、有楽町朝日ホールにて、第20回東京フィルメックスのコンペティション作品としてレイムンド・リバイ・グティエレス監督の長編初監督作『評決』が上映された。夫が妻と娘に振るった家庭内暴力を発端に、フィリピンの司法問題に鋭く切り込む野心作だ。現代フィリピン映画を牽引するブリランテ・メンドーサ監督がプロデューサーを務めていることでも話題となっている。


冒頭、市山尚三東京フィルメックス・ディレクターは、「この作品は一組の家族のドメスティック・バイオレンスを描くと同時に、フィリピンの司法手続きの問題をあぶり出すという社会的テーマを持った力作だと思いました。なにか具体的な事件がもとになっているんでしょうか?」と問いかけ。グティエレス監督は「実はドメスティック・バイオレンスに関する映画を作ろうと考えていたわけではありませんでした。ある日偶然、パートナーに暴力を振るわれた女性が、助けを求めて私の家にやって来たのがきっかけだったんです。そうした現場を目にしたのは初めてだったので、大きな衝撃を受けました。それでなにか自分にできることはないかという気持ちをずっと抱えていました。後々被害を受けた女性に話を聞いたところ、裁判に持ち込みたいということだったんですが、なんと数日後にふたりは元のさやに戻ったんですね。ひどいことがあったのにそれを忘れて元に戻れるのだろうかと思ったんですが、『法に訴えるにはあまりに煩雑な不都合がありすぎる』と彼女に言われたんです」と当時を振り返った。
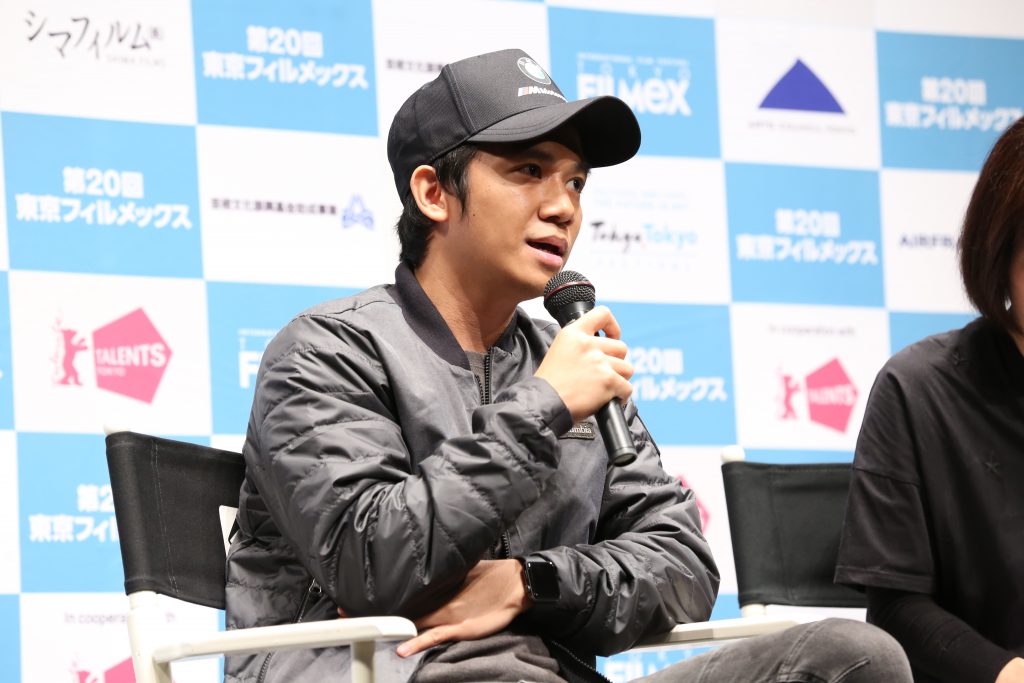
「司法問題以前に、警察の捜査の雑さが衝撃でした。相当な怪我なのに応急処置だけで被害者を振り回したり、流血沙汰を起こしたにもかかわらず被害者と加害者がずっと同行したり。実際、フィリピンの現状はどうなんでしょうか?」という観客からの質問に対しては、「この映画ではまず、フィリピンでの法のプロセスがどのように行われているかということを見せたいと思いました。実際、政府の方針としては家族優先、つまり家庭を壊さないためになるべく自分たちで解決してほしいという前提があるんですね。法的手段は機能しているといえば機能していますし、警察も仕事はしています。ただ、それが本当に有効なのかというとそうとは限らないわけですよね。人間誰しも落ち度があり、常にルールを順守できるとは限らない。法はあるけれども、法にも節穴はある。私が映画作家としてできることは、この映画で解決方法を提示するのではなく、いくつものカードをテーブルの上に並べて、『私たちの問題』として気づいてもらうこと。問題を解決するのは政府ではなく私たちなんだ、ということです」とグティエレス監督。


また「夫に用意された結末は、法廷では得ることのできなかった『正義』を、ほかの手段によって与えられたと受け取りました。監督はこの作品で、別の『正義』もありうるということを示したかったのでしょうか」と聞かれ、「それはぜひ観客のみなさんに決めてもらいたい。みなさんが考える『正義』を好きに解釈してもらいたいです。法的手続きが私たちの望む結果ではないこともあります。そのときに劇中では、もうひとつの『正義』が与えられた。でもそれは、夫がおかした罪に対して妥当な罰なのだろうか?ここで彼に下された結末は、法的なものよりもっと暴力的なものですよね」と回答。

質問は、今作のプロデューサーを務めたメンドーサ監督についてまで及んだ。「メンドーサ監督には、ドメスティック・バイオレンスというコンセプトは何度も題材にされているものだけど、君はそれでもやりたいのかと聞かれました。でもその現実を描きたかった。彼は長編の脚本を書き終えることができるなら、ぜひ読んで、自分の視点を加えて、映画化を考えてみようと言ってくださいました。脚本執筆にあたっては、ビン・ラウ監督の助けも得ました。撮影段階では、メンドーサ監督は本当に十分な自由を与えてくださって、自分の好きな解釈で撮ることができました。美的感覚が近いという意味でも、今作はメンドーサ風というのは否めないかもしれません。私が彼に教わったことは、観客はすべてわかっているという風に思わず、自分のストーリーをきちんと仕上げて、それを提示するということ。編集の段でも、ストーリーテリングにおいて常に自分に問いかける、自分を疑う、という助言をくださいました。そしてなにか間違いや欠点があっても、それも含めて自分のなかで良しとして次に進むということも学びました」と噛みしめるように話してくれた。

最後に「ラストシーンの妻の表情が、安堵しているようにも、哀しいようにも、自分を戒めているようにも見えました。どのような演技をつけたのでしょうか?」と問われると、「まず、監督はマジシャンのようなものだと思っているんです。自分のビジョンがあって、なんらかのトリックを持っていて、制作クルーや観客のみなさんをどれだけ触発しながら映画を仕上げられるか。それは俳優に関しても同じことが言えます。妻役で主演女優のマックス・アイゲンマンが現場に来た時、どんな人かというのをよく観察しました。そしてあえて演技指導をしなかった。考えすぎてほしくなかったし、自然に反応してほしかったから。一番難しかったのは最後、夫の結末に直面するシーンです。あの部分は本当に複雑な感情が入り混じっていると思ったので、彼女に解釈をゆだねて、外へ出て好きに歩いてとだけ伝えました。車にいきなり轢かれそうになるとか、どれくらいの距離をどこの方向に歩くかとか、言わなかったんですね。そして映画というのは、撮って終わりではない。編集もストーリーをガラッと変える力を持っているので、その段階でもどういうアングルで、どう繋げていくかよく考えました。映画のなかで観客がグッと掴まれたり刺さったりする部分があるとすれば、それはショックを受けるシーンがひとつあるからではなくて、全体の構成によって、盛り上がってできるものだと思うんですね。なのでそこに向けて、どういう風に観客を引き込むかということを常に考えていました」と締めくくった。


観客も監督もまだまだ話が尽きないといった様子だったが、時間になり終了となった。これを機に、家族、そしてそれを取り巻く社会のことを今一度考えてみてはいかがだろうか。
(文:福アニー、写真・明田川志保、白畑留美)

